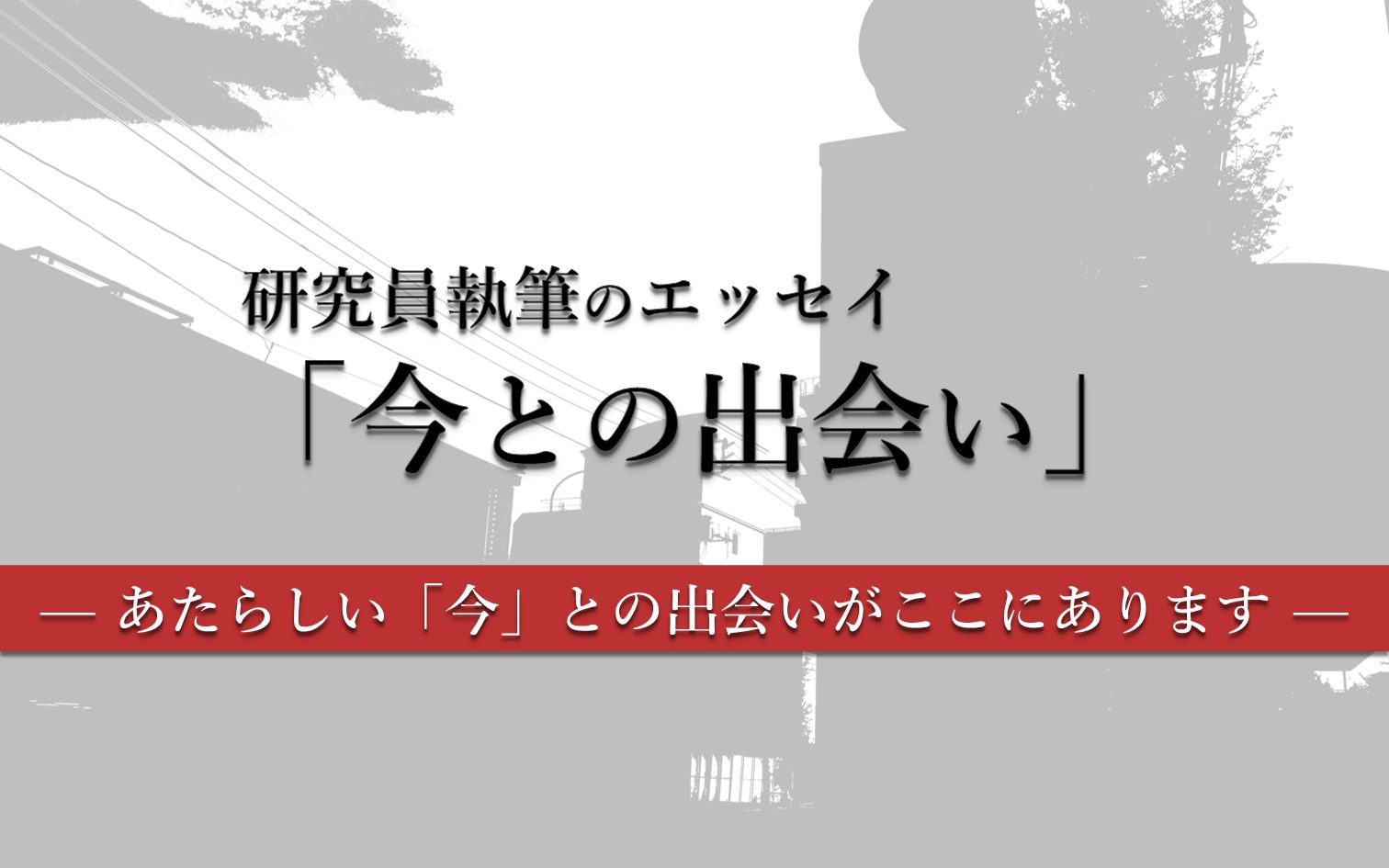今との出会い 第212回「疫禍の師走に想う「思い出の国」の人たち」

親鸞仏教センター嘱託研究員
伊藤 真
(ITO Makoto)
今年も師走を迎えた。本文執筆時点では、清水寺で毎年発表される「今年の漢字」はわからないが、多くの人がいくつかの共通の漢字を思い浮かべているのではないだろうか。今年は歴史に刻まれる疫禍の年となった。そんな一年を振り返って思うことは多々あるが、緊急事態宣言や外出自粛などの政策により、スポーツ、コンサート、舞台、展覧会や映画などを会場で「生(なま)」で体験する機会が失われたことも大きかった。もちろん命があってのことではあるが、文化・芸術にじかに触れることで触発されるものは大きいと改めて感じる。今回は、行政の、そして自分自身の気分的な規制もようやく緩和されつつあった10月に、地元横浜のKAAT神奈川芸術劇場で観ることができた2本の舞台作品について述べたい。
1本は同劇場芸術監督・白井晃演出の『銀河鉄道の夜2020』。25年前の作品の再演となる音楽劇だが、楽団のライブ演奏をバックに、「語り部」的な(賢治の妹トシの?)精霊・アメユキ(さねよしいさ子)の歌がイーハトーブの物語を引き出していく。原作もこの舞台作品も解釈は色々できるだろうが、脚本の能祖將夫は「亡くなった人はもちろん、生きている人の中にも、どれだけ会いたいと切望しても2度と叶わぬ人がいる……賢治は銀河鉄道を『思い出の国』に走らせたのだ」と述べている(同作品パンフレット)。『銀河鉄道の夜』には私自身の記憶と交錯する場面も多い。それが音と光の中で役者たちが躍動する舞台上の銀河鉄道に同乗してみると、本にも増して、時空を超えた感慨を呼び覚まされた。二十数年前、豪州の冬空高く輝く南十字星やさそり座を共に眺めた人たち。さらに遡れば、タイタニック号の悲劇の夜を語り聞かせてくれた生存者の英国の老婦人。鳥捕りの男がジョバンニらに雁を試食させるシーンでは、お菓子のような味だと言っているのに、なぜか番茶に浸したタラの塩漬けの一片を美味そうにしゃぶっていた(私が幼かった頃の)祖母を思い出した……。人の人生は多くの出会いと別れで紡がれているという当たり前のことを、舞台上の、そして私の心の中の「思い出の国」の人たちと出会って改めて感じた。
もう一本の舞台作品は、ユヴァル・ノア・ハラリの『サピエンス全史』に想を得て、「人類すべての成長物語」を構想したという谷賢一の作・演出による『人類史』。第一幕は人類が言葉や文化・芸術を生み出すまでを、イスラエルのダンサー、エラ・ホチルドがオンラインで振り付けたという身体表現(ダンス)で描き、権力の発生とその犠牲になる青年を描いた場面はギリシャ悲劇を思わせた。そして科学革命から現代までをエネルギッシュな群像劇で描く第二部はミュージカル仕立て(作品全体の音楽は志磨遼平)。200万年の時を3時間弱に詰め込む難しさは否めないが、ストーリーも演出もてんこ盛りの贅沢なこの作品で印象に残ったのは、人類が死者の追悼を始めた太古の葬送のしめやかな場面だった。村の長老と司祭を兼ねた役回りの「老人」(山路和弘)が、われわれの生は多くの死者たちの上にあることを残された者たちに語る。その意味で、壮大な「人類の成長物語」はまた、人類にとっての「思い出の国」の住人たちに対する、挽歌であり、讃歌でもあると感じた。
席は一つ空きで会話も控えめ、当然ながら常時マスク着用、飲食も禁止だから幕間のロビーでのグラス一杯のワインもおあずけ…。そんな中でも劇場で「生(なま)」で触れることができた二本の作品が私の心身に沁み渡らせてくれたのは、私たちの今が、私たちの人生や人類の歴史を形作って「思い出の国」へと去っていった人たちと共にあるということ。疫禍に揺れた今年、そのことのかけがえのなさに力を得つつ、同時にまたその切なさをも噛みしめる師走である。
(2020年12月1日)
最近の投稿を読む

今との出会い 第231回「病に応じて薬を授く」
2022年8月01日
今との出会い 第231回「病に応じて薬を授く」 親鸞仏教センター主任研究員 加来 雄之 (KAKU Takeshi) 「また次に善男子、仏および菩薩を大医とするがゆえに、「善知識」と名づく。何をもってのゆえに。病を知りて薬を知る、病に応じて薬を授くるがゆえに。」(『教行信証』化身土巻、『真宗聖典』354頁)…
続きを読む

今との出会い 第230回「本願成就の「場」」
2022年6月01日
今との出会い 第230回「本願成就の「場」」 親鸞仏教センター嘱託研究員 中村 玲太 (NAKAMURA Ryota) 「信仰を得たら何が変わりますか?」――訊ねられる毎に苦悶する難問であり、断続的に考えている問題である。これは自身の研究課題とする西山義祖・證空(1177…
続きを読む

今との出会い 第229回「哲学者とは何者か」
2022年5月01日
今との出会い 第229回「哲学者とは何者か」 親鸞仏教センター嘱託研究員 越部 良一 (KOSHIBE Ryoichi) 今、ヤスパースの『理性と実存』を訳しているので、なぜ自分がこうしたことをしているのかを書いて見よう。…
続きを読む

今との出会い 第228回「喪失の「永遠のあとまわし」―『トロピカル〜ジュ!プリキュア』論―」
2022年4月01日
今との出会い 第228回「喪失の「永遠のあとまわし」―『トロピカル〜ジュ!プリキュア』論―」 親鸞仏教センター嘱託研究員 長谷川 琢哉 (HASEGAWA Takuya) 娘が4歳になって幼稚園に通うようになると、プリキュアを見るようになった。それまでは恐竜や妖怪の人形でおままごとをしていた娘が幼稚園の友達の影響でプリキュアを見るようなったことに対しては、感慨とともに若干の寂しさを覚えたが、私が日曜朝の『トロピカル~ジュ!プリキュア』(以下、『トロプリ』。ABCテレビ・テレビ朝日系列にて放送)を娘と一緒に楽しみにするようになるまでほとんど時間はかからなかった。…
続きを読む
No posts found