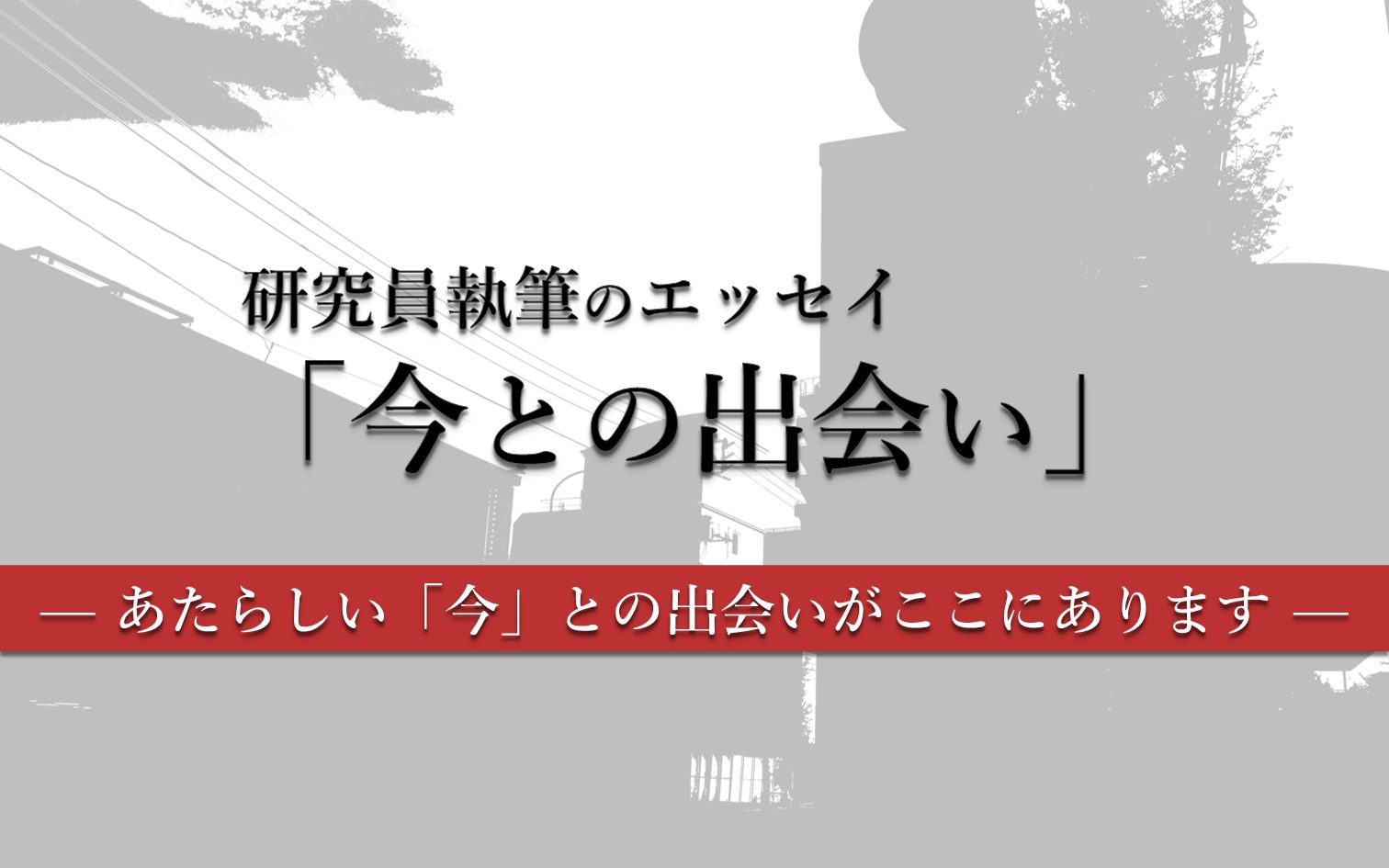今との出会い第201回「演じる―山崎努と一休に寄せて―」

親鸞仏教センター嘱託研究員
飯島 孝良
(IIJIMA Takayoshi)
或る時期までの俳優には、どこか思想家のようなところがあったと評したのは、名うてのテレビ批評家・ナンシー関だった(『何をいまさら』角川書店、1993、42頁)。自分自身が憧れた三船敏郎や勝新太郎は、「男たるもの、かかる野性味溢るる渡世人たるべし」と思わせるスタアそのものだった。その一方で、岸田森や成田三樹夫のように妖艶なまでの表現者に魅かれもした。そうした名優がずば抜けた「色気」を呈していた所以は、もしかすると徹底した洞察と思索の結晶として人間を表現してみせた、その姿にあったのではないか。狂気に近いほどに人間の業を見せつけてくるその演技は、どこまでも深く人間と世界と歴史を理解しようとした結果として顕れたものと感じられてくるのである。
山崎努氏は、まさにそうした思想家の如き俳優の面目を教えてくれる。山崎氏について直ちに思い浮かぶのは、何といっても黒澤明監督の『天国と地獄』(1963)での名演である。「地獄」と表すべき貧しい生い立ちと社会格差への拭い難き怨念を絶叫するその姿は、観客の胸を掻きむしってくる。この作品については自身でも思い入れは相当あるようで、「へただなあ、今ならもっとうまくやるけどなあと思いつつ、でもあの若僧の青臭いうっとうしさや稚拙な虚勢の張りようはあの時の姿であってもう絶対に再現できない、演技とはすぐに腐ってしまう生(な)まものなのだ、いや腐ってゆく「状態」そのものなのだとあらためて感じたりした」(山崎努『柔らかな犀の角』文藝春秋、2012、154頁)。お察しの通り、この『柔らかな犀の角』という書名は、釈尊のことば――「犀の角の如くただ独り歩め」(『スッタニパータ』)に由来しており、「何をするにも自信がなく、毎日が手探り及び腰、そのくせ鼻っ柱だけは強く、事あるごとにすぐ開き直る。そんな臆病な若造」(前掲書、9頁)だった山崎氏は、この「犀の角の如くただ独り」の一句が気に入っていたのだという。と同時に、多くの演劇作品や朋友や書物との旺盛な交流を通して、山崎氏は静謐な洞察と思索を深めてこられた。
山崎氏に関して、もうひとつ印象に刻まれたものがある。山崎氏は、何とも美味そうに食うのである。伊丹十三監督『タンポポ』(1985)でのラーメンにせよ、滝田洋二郎監督『おくりびと』(2008)での焼き白子にせよ、こちらが喉を鳴らすほど美事に食ってみせる。その演技ほど、食が人間の生の根源に接する契機だと実感させるものはない。そうして、食を共にすることの歓びも、そこには漂っている。「美食家は生活を楽しんでいる。対人関係において懐が深い」(前掲書、214頁)という山崎氏には、確かに食への並々ならぬこだわりが感じられる。
山崎氏から自分が再認識させられたのは、我々が人間を洞察し思索しようとし、そして日常へと関わろうとすれば、そのどこかで或る「振る舞い」をせざるを得ないのではないか、ということである。社会の中で自らを定位しようとすれば、赤裸の自己などというものを立てることは極めて難しい。いわば、「自己とは何か」を不可避的に考え、表現せざるを得ないのではないか。そう考えれば、ことは狭義の演劇論に留まらない。「演じる」ということそのものが、歓びも悲しみもする我々の生と死には不可分であるように思われてくるのである。
***
一休宗純は、或る久参の居士を「十一面、那个(なこ)か正面」と評した(一休宗純賛「宝岩祐居士肖像」京都・酬恩庵蔵)。『臨済録』の句を借りて「十一面観音のごとく、どの顔が本当の顔かわからん」というのである。実はこの句こそ、一休その人を自ら評したものとも思える。というのも、一休は自らの悟道と伝統を担う矜持を表明しながらも破戒を繰り返し強調するなど、自らの矛盾と時代の堕落を真っ直ぐ見据えて生きた多面的な性格がみえるからである。一休は、自己と他者の在り方を決して妥協することなく追究し、そのために独立不羈であることを辞さなかった(これについては、芳澤勝弘「一休の墨蹟」〔『別冊太陽 一休』平凡社、2015、121頁〕を参照)。
人間ならば、どんなに親しい間柄であっても、その「正面」はそうたやすくみえるものではない。ことによると、その「正面」は十面も二十面もあるかもしれない。もし「正面」がひとつだけだとしたら、人間は何と単調で味気ないことか。「あんな人だと思わなかった」などということばが聞かれるけれども、結局は周囲がみえるところしか眼を向けていなかった、というに過ぎない。我々の人格としての「自己」が他者との関係性のなかに存在していると述べたのは、精神病理学者の木村敏氏である(『関係としての自己』みすず書房、2005)。言い得て妙である。
我々が関わる「場」において、公人として、家庭人として、さまざまに「正面」をみせる。そしてそのどれもが自己である。その意味で、生と死をごまかさず考え抜く山崎氏のことばに、只々謹聴する次第である。
そもそも人間はなーんにもわかっていない生き物なのだ。【中略】まごついているうちに寿命が尽きてきて、そろそろご臨終かとなる。これがふつうの人生パターン。この最後に直面する臨終が、最大の難事のようだ。まあ僕などはかなり図々しくなっているから、こと最期に関しては案外あっさりと受け容れてしまうような気もするが、しかしこれとてその場になってみなければわからない。いずれにしても人間のプロなんていないのだ。 (前掲書、318~319頁)
演技を生業としていない者であっても、世界と歴史と人間の只中に自らを定位すること=「演じる」ということを、自身の生の営みとして観照/鑑賞せねばならないのであろう。そのとき、まさしく『スッタニパータ』58番目の韻文にいう如く、学識豊かで真理をわきまえた高邁明敏な友と交わりつつ、犀の角の如くただ独り歩んでいくのではないか。
(2020年2月1日)
最近の投稿を読む

今との出会い第201回「演じる―山崎努と一休に寄せて―」
2022年9月29日
今との出会い第201回「演じる―山崎努と一休に寄せて―」 親鸞仏教センター嘱託研究員 飯島 孝良 (IIJIMA Takayoshi) 或る時期までの俳優には、どこか思想家のようなところがあったと評したのは、名うてのテレビ批評家・ナンシー関だった(『何をいまさら』角川書店、1993、42頁)。自分自身が憧れた三船敏郎や勝新太郎は、「男たるもの、かかる野性味溢るる渡世人たるべし」と思わせるスタアそのものだった。その一方で、岸田森や成田三樹夫のように妖艶なまでの表現者に魅かれもした。そうした名優がずば抜けた「色気」を呈していた所以は、もしかすると徹底した洞察と思索の結晶として人間を表現してみせた、その姿にあったのではないか。狂気に近いほどに人間の業を見せつけてくるその演技は、どこまでも深く人間と世界と歴史を理解しようとした結果として顕れたものと感じられてくるのである。…
続きを読む
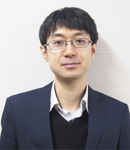
今との出会い 第232回「漫画の中の南無阿弥陀仏」
2022年9月09日
今との出会い 第232回「漫画の中の南無阿弥陀仏」 親鸞仏教センター嘱託研究員 青柳 英司 (AOYAGI Eishi) 日本の仏教史において、南無阿弥陀仏という言葉が持った意味は極めて重い。 この六字の中に、法然は阿弥陀仏の「平等の慈悲」を発見し、親鸞は一切衆生を「招喚」する如来の「勅命」を聞いた。彼らの教えは、身分を越えて様々な人の支援を受け、多くの念仏者を生み出すことになる。そして、現代においても南無阿弥陀仏という言葉は僧侶だけが知る特殊な用語ではない。一般的な国語辞典にも載っており、広く人口に膾炙(かいしゃ)したものであると言える。…
続きを読む

今との出会い 第231回「病に応じて薬を授く」
2022年8月01日
今との出会い 第231回「病に応じて薬を授く」 親鸞仏教センター主任研究員 加来 雄之 (KAKU Takeshi) 「また次に善男子、仏および菩薩を大医とするがゆえに、「善知識」と名づく。何をもってのゆえに。病を知りて薬を知る、病に応じて薬を授くるがゆえに。」(『教行信証』化身土巻、『真宗聖典』354頁)…
続きを読む

今との出会い 第230回「本願成就の「場」」
2022年6月01日
今との出会い 第230回「本願成就の「場」」 親鸞仏教センター嘱託研究員 中村 玲太 (NAKAMURA Ryota) 「信仰を得たら何が変わりますか?」――訊ねられる毎に苦悶する難問であり、断続的に考えている問題である。これは自身の研究課題とする西山義祖・證空(1177…
続きを読む
No posts found