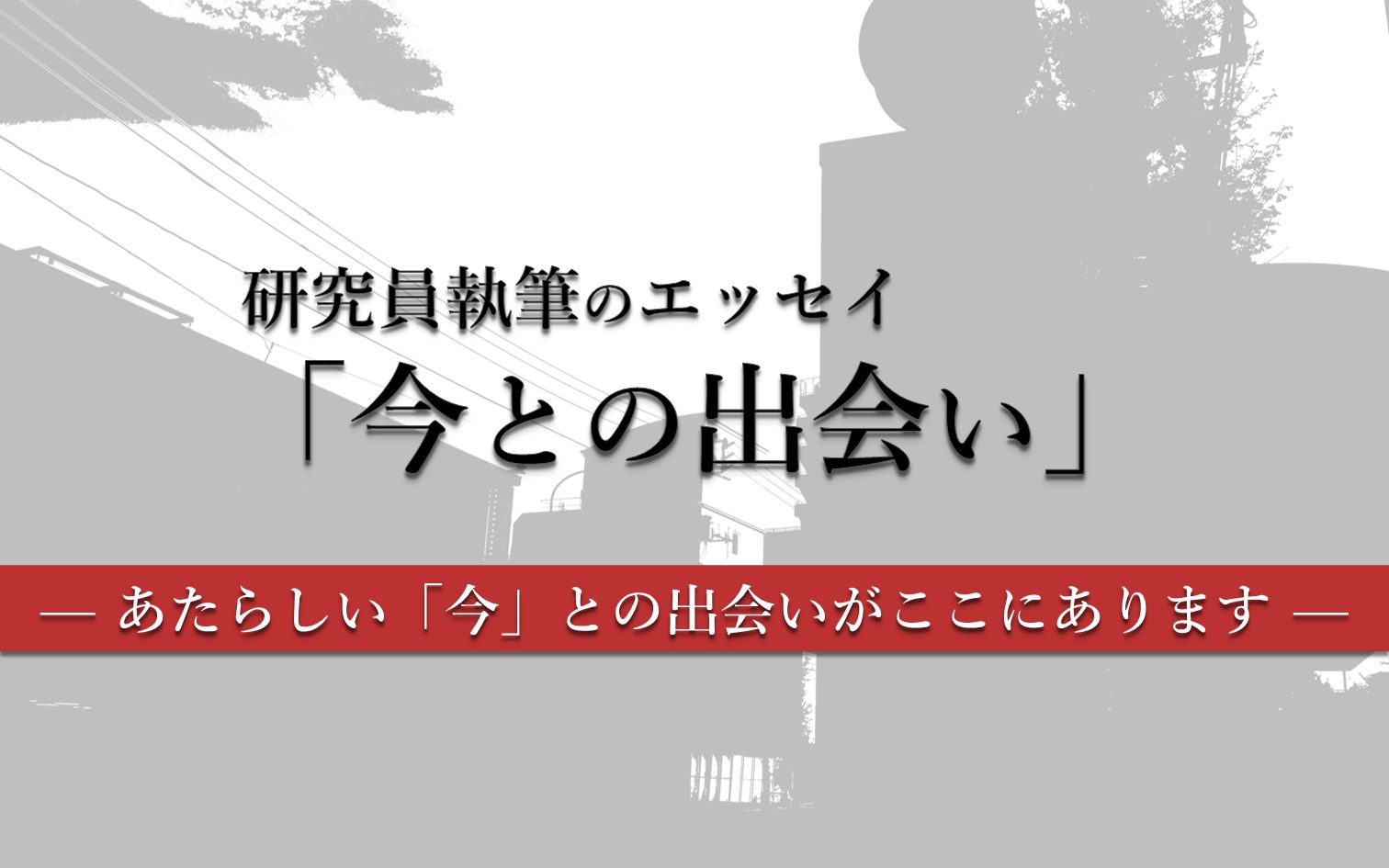今との出会い第199回「曖昧なブラック」

親鸞仏教センター嘱託研究員
中村 玲太
(NAKAMURA Ryota)
9月18日。染め上げられた緑が静寂に圧倒されるのも束の間、それはまるで王蟲のように、一気に場面は赤くなる。叫べ。
歌人・穂村弘は「共感(シンパシー)」と「驚異(ワンダー)」について度々言及するが、『短歌という爆弾――今すぐ歌人になりたいあなたのために』(小学館、2000)にはまさに「共感と驚異」という章でその両者の共振が生む短歌の魅力を解説している。ここでは共感と驚異の共振性が解説されているが、『整形前夜』(講談社文庫、2012)になると「驚異」に力点を置いた――「共感」が溢れる社会への警鐘を促す論へと軸足が動いているように思われる。『整形前夜』には以下のようにある。
何かに感動する人間って鈍感なんじゃないか、と思うことがある。中学生のとき、世界の名作文学を何冊読んでも何も感じなかった。大人になって改めて読み直してみてその面白さに驚いたのだが、これは経験を積んで作品の魅力がより深くわかるようになったということなのだろうか。どうも違うような気がする。加齢と共に「驚異」を「驚異」のままキャッチする能力が衰えて「共感」に変換して味わうようになったのではないか。
(「共感と驚異 その3」より)
この最後の一文にドキッとするわけであるが、これは他者理解でも言えることではないのか。そう思うと余計に考えてしまう。以前ほど対人関係に息苦しさを感じなくなったのは、他者という〈驚異〉そのものをうまく「共感」へと変換しているからではないか。自分の言葉で他者を翻訳・一般化し、他者を理解可能な物語の中で消化できるようになる。それは生きていく上で不可避なことであり、これが大人になるということなのでもあろう。
しかしこの「共感」の物語にこそ息苦しさを感じていたのではなかったのか。違う現実を生きる我々はそれだけで本来〈驚異〉そのものだと思う。うまく共感へと変換できない、そのまま驚異としてキャッチするしかないものも多数あるはずだ。共感が求められる社会で驚異が行き場を失い、共感の範疇から疎外された存在を無視してはいないだろうか。置き去りにされた「よくわからない」自己/他者に再び目を向けることはできるのだろうか。僕の心には共感が溢れている。
年末に向けて脱線しておこう(いや復線だ)。今年2月にMVが公開された欅坂46「黒い羊」は、共感の範疇から疎外された「僕」の物語であると一応は言えよう。ここで注目したいのは、「黒い羊」のMVを監督した新宮良平の言葉だ。センターの平手友梨奈について語った言葉である。
“僕”というのは平手さんそのものだと思っている。彼女はメンバーとかいろんな大人の中で、心を打ちひしがれているわけです。まさに「黒い羊」そのものというか。平手さんがみんなの前で「私はこれでいい」と言い切るシーンがどうしても作りたかったのはあります。
平手友梨奈は、パフォーマンスの舞台上を「自分が自分でいられる環境」(『ROCKIN’ON JAPAN』2019年4月号、173頁)とするが、作品世界上でまさに“僕”が“僕”となる――あるいは「なれない」そのリアルを目撃するわけである。「自分が自分でいられる環境」と言うが、特に2017年夏以降必ずしも舞台上で順風満帆であったわけではないことは多くの人が知るところであろう。動けないことへの批判は数多あった。全国ツアー2018も、調子が良かったとはまず言えないパフォーマンスであったが、「自分が納得いってないステージになぜ立たなきゃいけないのかっていうことを、考えて考えてやってました。毎公演、毎公演、スタッフさんと話して、出るのか出ないのかっていう話をして」(前出、174頁 ※ライブ演出についてストーリー性のぶれ等を問題にしている)と語っている。
ロキノンを読めば分かるが、決して平手友梨奈は開き直っているわけではない。しかし、考えすぎてしまう自分をやめれば楽になるのに、と言いながら、そうやって楽になった自分についての想像は、「まったくつかない。うん。たぶん全部をはっきりさせたいから。はっきりさせないとダメだから」(前出、178頁)と。こうしたところを含めて我々は、“僕”が“僕”になるという意味を目前で問われるわけである。自分を誤魔化さない、このシンプルな言葉が現実に実行される時、現在進行形で様々な波紋を呼んでいる――「共感」の物語に仕立てられたらどんなに楽か!という現にそこかしかに在るはずの〈驚異〉の暴力性と魅力をそこに感じる。
9月19日。東京ドーム。5万人の聴衆を前に、「らしさって一体何?」と問いながら彼女は一人で最後の幕を閉めた。
(2019年12月1日)
最近の投稿を読む

今との出会い第199回「曖昧なブラック」
2022年9月29日
今との出会い第199回「曖昧なブラック」 親鸞仏教センター嘱託研究員 中村 玲太 (NAKAMURA Ryota) 9月18日。染め上げられた緑が静寂に圧倒されるのも束の間、それはまるで王蟲のように、一気に場面は赤くなる。叫べ。…
続きを読む
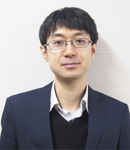
今との出会い 第232回「漫画の中の南無阿弥陀仏」
2022年9月09日
今との出会い 第232回「漫画の中の南無阿弥陀仏」 親鸞仏教センター嘱託研究員 青柳 英司 (AOYAGI Eishi) 日本の仏教史において、南無阿弥陀仏という言葉が持った意味は極めて重い。 この六字の中に、法然は阿弥陀仏の「平等の慈悲」を発見し、親鸞は一切衆生を「招喚」する如来の「勅命」を聞いた。彼らの教えは、身分を越えて様々な人の支援を受け、多くの念仏者を生み出すことになる。そして、現代においても南無阿弥陀仏という言葉は僧侶だけが知る特殊な用語ではない。一般的な国語辞典にも載っており、広く人口に膾炙(かいしゃ)したものであると言える。…
続きを読む

今との出会い 第231回「病に応じて薬を授く」
2022年8月01日
今との出会い 第231回「病に応じて薬を授く」 親鸞仏教センター主任研究員 加来 雄之 (KAKU Takeshi) 「また次に善男子、仏および菩薩を大医とするがゆえに、「善知識」と名づく。何をもってのゆえに。病を知りて薬を知る、病に応じて薬を授くるがゆえに。」(『教行信証』化身土巻、『真宗聖典』354頁)…
続きを読む

今との出会い 第230回「本願成就の「場」」
2022年6月01日
今との出会い 第230回「本願成就の「場」」 親鸞仏教センター嘱託研究員 中村 玲太 (NAKAMURA Ryota) 「信仰を得たら何が変わりますか?」――訊ねられる毎に苦悶する難問であり、断続的に考えている問題である。これは自身の研究課題とする西山義祖・證空(1177…
続きを読む
No posts found