
今との出会い 第179回「「女人往生」について――舞台『彼の僧の娘』を見る」

親鸞仏教センター研究員
長谷川 琢哉
(HASEGAWA Takuya)
昨年たまたま私が入居した部屋のオーナーが、ある舞台の制作に関わっておられる方で、公演のチラシをいただいた。「女人往生環」と題されたその舞台は、仏伝に登場するパターチャーラーと、大逆事件で獄死した真宗僧侶高木顕明の娘を題材とした二つの芝居を上演するものだった。不思議としか言いようのない縁に導かれ、私はその舞台を見に行った。
二人の苦悩する女性を題材とした二つの芝居は、伝統的に仏教的な解脱・救済からやや遠ざけられた存在として位置づけられてきた女性の救済を描いたものだ。どちらからも強烈な印象を受けたが、近代仏教を研究している私にとっては、とくに高木顕明の娘を題材とした『彼の僧の娘』に深く考えさせられた。
劇中で「高世」と呼ばれる芸者は、高木顕明の養女・加代子をモデルとしている。高世は天皇暗殺を企てた「逆賊」の娘として寺を追われ、芸者に売られた。公安警察に監視され、不当な差別の中で苦悩する高世は、自らの陥った境遇の中で、必死に救いを求める。彼女は父である「彼の僧」と心の中で対話する。
(娘)「私がいる意味……どこにあるんや?ここまで苦しんで…拾われ、捨てられ…足蹴にされて…うちは道の石ころなんや」
(父)「それでも必ず弥陀は救う。よきひと、あしきひと、尊き人、いやしき人を嫌わず選ばれず、先にこれを導きたまう。石、瓦、つぶてのごとくなる我らなり。……既に人の生を受けた。佛の教えもすでに聞いた。わしの姿をしった。」
(娘)「わからへん!わからへん!何一つ、私にはわからへん!」
(父)「もう知っている。さあ、そのまま行け。生まれた命は皆、等しく尊い。往き生まれ、無上に尊いいのちがお前にもわしにもある。」
(娘)「ほんまに?……お父ちゃん!……私が居る意味……私が居る…」
(父)「救うから安心せよ、護るから心配するな。わしの辿(たど)った道を、お前も訪(とぶ)らうのだ。さあ立て、さあ、一歩、一歩……わしは先を歩いておる。さあ、進め。」
作・演出を手がけた嶽本あゆ美の脚本は、鋭く迫ってくるものだった。真宗大谷派の寺の娘として育ちながら、国家や共同体から排除されつつあった高世は、阿弥陀如来の救済を説く父の言葉と自分自身の境遇の間で大きく揺れ動く。伝統的な仏教において女性が解脱や救済から一歩遠のいた存在であるとしても、親鸞の教えからすれば、それならなおのこと女性は救われるはずである。実際、作中の最後で高世は、敗戦後の廃墟の中で次のように言う。
「きっとこの世に極楽だって来ることがある。どんな爆弾でも吹き飛ぶことがないものが、きっと心の中なら持てるんやで。さあ、立って歩こう」
女性であることによって与えられる苦しみと、女性の救済。最終的に高世は、この世での救済、この世での往生という境地を見いだしていくのである。
もちろんここには、簡単に済ますことのできない仏教における女性性の問題というものが相変わらず存しているし、それは真宗学や仏教学の観点からも真摯に受け止めるべきものであるだろう。実際私が専門としている近代仏教というフィールドにおいても、女性に焦点が当てられることはそう多くはない(『近代仏教スタディーズ』に「女性仏教者」という項目があるのは重要なことである)。「女人往生」という問題は、一種特別な問いを、私たちに突きつけてくる。
ところで、最後に気になったことがあった。劇中でははっきりと描かれていないが、実際の高木加代子は晩年、天理教に帰依し教会主にまでなったという。高木顕明の娘は、なぜ浄土真宗ではなく、天理教に救いを求めたのだろうか。実際のところはわからない。ただ、一般に、戦中の国家家族観の中に組み込まれてしまった伝統的な仏教教団は、ひとたび「国家家族」の枠組みから排除された人々にしっかりと教えを伝えることがはたしてできたのだろうか。あるいはここに困難があったのかもしれない。このこともまた、現代を生きる私たちにとってひとつの問いとして残されるものであるだろう。
(2018年4月1日)
最近の投稿を読む

今との出会い第240回「真宗の学びの原風景」
2023年7月01日
今との出会い第240回「真宗の学びの原風景」
親鸞仏教センター主任研究員
加来 雄之
(KAKU Takeshi)
今、私は、親鸞が浄土真宗と名づけた伝統の中に身を置いて、その伝統を学んでいる。そして、その伝統の中で命を終えるだろう。
この伝統を生きる者として私は、ときおり、みずからの浄土真宗の学びの原風景は何だったのかと考えることがある。
幼い頃の死への戦きであろうか。それは自我への問いの始まりであっても、真宗の学びの始まりではない。転校先の小学校でいじめにあったことや、高校時代、好きだった人の死を経験したことなどをきっかけとして、宗教書や哲学書などに目を通すようになったことが、真宗の学びの原風景であろうか。それは、確かにそれなりの切実さを伴う経験あったが、やはり学びという質のものではなかった。
では、大学での仏教の研究が私の学びの原風景なのだろうか。もちろん研究を通していささか知識も得たし、感動もなかったわけではない。しかしそれらの経験も真宗の学びの本質ではないように感じる。
あらためて考えると、私の学びの出発点は、十九歳の時から通うことになった安田理深(1900〜1982)という仏者の私塾・相応学舎での講義の場に立ち会ったことであった。その小さな道場には、さまざまな背景をもつ人たちが集まっていた。学生が、教員が、門徒が、僧侶が、他宗の人が、真剣な人もそうでない人も、講義に耳を傾けていた。そのときは意識していなかったが、今思えば各人それぞれの属性や関心を包みこんで、ともに真実に向き合っているのだという質感をもった場所が、確かに、この世に、存在していた。
親鸞の妻・恵信尼の手紙のよく知られた一節に、親鸞が法然に出遇ったときの情景が次のように伝えられている。
後世の助からんずる縁にあいまいらせんと、たずねまいらせて、法然上人にあいまいらせて、又、六角堂に百日こもらせ給いて候いけるように、又、百か日、降るにも照るにも、いかなる大事にも、参りてありしに、ただ、後世の事は、善き人にも悪しきにも、同じように、生死出ずべきみちをば、ただ一筋に仰せられ候いしをうけ給わりさだめて候いしば……
(『真宗聖典』616〜617頁)
親鸞にとっての「真宗」の学びの原風景は、法然上人のもとに実現していた集いであった。親鸞の目撃した集いは、麗しい仲良しサークルでも、教義や理念で均一化された集団でもなかったはずである。そこに集まった貴賤・老若・男女は、さまざまな不安、困難、悲しみを抱える人びとであったろう。また興味本位で訪れてきた人や疑念をもっている人びともいただろう。その集まりを仏法の集いたらしめていたのはなにか。それは、その場が、「ただ……善き人にも悪しきにも、同じように」語るという平等性と、「同じように、生死出ずべきみちをば、ただ一筋に」語るという根源性とに立った場所であったという事実である。そうなのだ、平等性と根源性に根差した語りが実現している場所においてこそ、「真宗」の学びが成り立つ。
このささやかな集いが仏教の歴史の中でもつ意義深さは、やがて『教行信証』の「後序」に記される出来事によって裏づけられることになる。そして、この集いのもつ普遍的な意味が『教行信証』という著作によって如来の往相・還相の二種の回向として証明されていくことになるのである。親鸞の広大な教学の体系の原風景は、このささやかな集いにある。
安田理深は、この集いに、釈尊のもとに実現した共同体をあらわす僧伽(サンガ)の名を与えた。そのことによって、真宗の学びの目的を個人の心境の変化以上のものとして受けとめる視座を提供した。
本当の現実とはどういうものをいうのかというと、漠然たる社会一般でなく、仏法の現実である。仏法の現実は僧伽である。三宝のあるところ、仏法が僧伽を以てはじめて、そこに歴史的社会的現実がある。その僧伽のないところに教学はない。『選択集』『教行信証』は、僧伽の実践である。
(安田理深師述『僧伽の実践——『教行信証』御撰述の機縁——』
遍崇寺、2003年、66頁)
「教学は僧伽の実践である」、このことがはっきりすると、私たちの学びの課題は、この平等性と根源性の語りを担保する集いを実現することであることが分かる。また、この集いを権力や権威で否定し(偽)、人間の関心にすり替える(仮)濁世のシステムが、向き合うべき現代の問題の根底にあることが分かる。そしてこのシステムがどれほど絶望的に巨大で強固であっても、このささやかな集いの実現こそが、それに立ち向かう基点であることが分かる。
私は、今、自分に与えられている学びの場所を、そのような集いを実現する場とすることができているだろうか。
(2023年7月1日)
最近の投稿を読む…
続きを読む

今との出会い第239回「Aの報酬がAであるという事態」
2023年6月01日
今との出会い第239回「Aの報酬がAであるという事態」
親鸞仏教センター嘱託研究員
越部 良一
(KOSHIBE Ryoichi)
私はいったいいつから哲学し出したのか、という問いに、私はこう考えることにしている。それは12歳の時、ビートルズの「A…
続きを読む

今との出会い第238回「寺を預かる」
2023年4月01日
今との出会い第238回「寺を預かる」
親鸞仏教センター嘱託研究員
田村 晃徳
(TAMURA Akinori)
学ぶ喜びは知識を得ることであるが、学びにより発見されるのは自分の無知であろう。人は無知と言われないように学ぶ面がある。「無知の知」とは古来より伝わる大切な言葉だ。しかし、この言葉には無知である自分を蔑むニュアンスはない。それどころか、無知であることに気づいた自分のことを誇ってさえいるようにも聞こえる。学びとは知識を得ることではない。知識を得ることを通じ、自分を知ることにその目的はある。
歴史を学ぶ喜びも同様である。歴史的事項を知ることはとても楽しい。しかし事項を知るだけではただの物語だろう。それが、どのように今日の自分と関わりをもつか。このことを考えることにより自身に肉薄した事実として理解されるだろう。その時に、気づくことはただ一つ。私は先人達の努力により、今ここで生きていることができているということである。
その先人とはもちろん、祖父や父も含む。しかし、寺を支えてくれた門徒の皆さんも当然入る。門徒の方を支えてくれた、そのご家族も含むだろう。さらには、信仰を伝えてくれた先人達も含まれるだろう。このように遡っていくならば、いつかは親鸞聖人や釈尊にもつながるに違いない。
そのように考えるときに、住職達がよく使う大切な言葉を思い出した。それは「お寺を預かる」という表現である。当然のことであるが、住職が「ここは自分の寺だ」などと言い出したら、そのお寺はおしまいである。そうさせない大切な発想。それが「預かる」というものだろう。つまり、私は今、預かっているお寺において、先人達により伝えられた仏法に出遇うというご縁をいただいているのだ。親鸞聖人も『歎異抄』でお釈迦様や善導大師の名を挙げて、伝えられてきた仏法に出会えた喜びを述べている。そこに浄土真宗は自分の教えだ、といった傲慢さは皆無である。親鸞聖人もいただいた法を後世に伝えられた。それが今、私にまで伝わっている。ならば私のやるべき事も同じである。法を後世に伝えることである。
寺の歴史を学ぶ。それは知的関心だけではない。一つのお寺が誕生するまでには、悠久の仏法や、人々の歴史が必要であったことを知る。それは住職としての責任感を改めて自覚させる気づきなのである。
(2023年4月1日)
最近の投稿を読む…
続きを読む

今との出会い第237回「本当に守るべきものを明らかにする」
2023年3月01日
今との出会い第237回「本当に守るべきものを明らかにする」
親鸞仏教センター嘱託研究員
菊池 弘宣
(KIKUCHI Hironobu)
「あわれ、生きものは互いに食(は)み合う」
(なんと悲しいことか、生きものはお互いに争い食らい合っている)
それは、お釈迦さまの少年時代、農耕祭に臨まれた時のことである。土の中から一匹の虫が這い出てくるところに、一羽の鳥がやって来て、ついばむやいなや、飛び去っていった。それをじっと見ておられた悉多太子(しったたいし、釈尊の成道以前の名)が、深い悲しみの中より発せられた言葉であると、仏伝は伝えている。(以上、信國淳『無量寿の目覚め』〔樹心社、2005年〕所収「「個人」と「衆生」」、26頁取意)
大谷専修学院という場の基礎を築いた信國淳先生は、以下のように、「生類相克(そうこく)」を目の当たりにした少年太子の胸中に思いをいたす。
この場合太子の胸は、すべての生きものへの同苦共感の世界に生きたのである。鳥からついばまれる虫と、虫を食っていのちを養う鳥と、そのいずれにも与することなく、そのいずれをも生き、そのいずれにおいても、太子自らが生きている生命との交感、交流を感じつつ、そこに衆生世界を感得し、「あわれ、生きものは互いに食み合う」と、その如実知見を表白したのである。
(同前、26頁~27頁)
「そのいずれにも与(くみ)することなく」という一言が、私の心に残っている。食われ殺される側、食い殺す側、そのどちらか一方を支持し、正当化するというのではない。そのようなメッセージとして受け取った。思い起こされるのは、私自身の少年時代、遠足に出掛けた時のことである。一羽のアゲハチョウが、カマキリに捕まり、今まさに食われようとしている場面に遭遇した。それを見て私は、「かわいそうに。なんてひどいことをするんだ」と思い、蝶の羽からカマキリの鎌を引き離し、助けてあげた。すると、蝶はすっと飛び立っていったが、今度は、カマキリがぐったりとして動かなくなってしまった。それを見て私は、「なんてことをしてしまったんだ」とショックを受けた。カマキリは、力尽きて死んでしまったのかもしれない。どうなったのか、その顛末を見届けることはできなかった。その時のことが思い起こされてくるのである。
その時のカマキリと同じように、私自身は平生、食い殺す側になっている。自分が直接手を下さずとも、誰かに頼って、他の生き物のいのちを奪っている。他の生き物を殺して食べなければ、自身のいのちを継ぐことはできない。自分という存在は、無数の生き物たちの犠牲の上に成り立っていると言える。
さらに言えば、私は、ゴキブリやムカデなどのいわゆる害虫は、容赦なく殺してきている。害をもたらすと感じるものを何であれ、都合によって殺すような自分だから、もしも戦場に出るようなことになったら、ためらいなく人を殺してしまうのではないかと危惧している。
一方で時には、食われ殺される側に自分の身を置くということも起こり得るのかもしれない。しかし、正直に言って、食われたくないし、殺されたくない。要するに、あきらめが悪いのである。その心中は、仏陀釈尊が、『法句経』(ダンマパダ)に説かれている通りである。
一二九 すべての者は暴力におびえ、すべての者は死をおそれる。己が身をひきくらべて、殺してはならぬ、殺さしめてはならぬ。
一三〇 すべての者は暴力におびえる。すべての(生きもの)にとって生命は愛(いと)しい。己が身にひきくらべて、殺してはならぬ、殺さしめてはならぬ。
(中村元訳『ブッダ真理のことば・感興のことば』ワイド版岩波文庫、28頁)
私自身は、自分にも、他者にも、殺されたくないのである。存在を尊重されたい、尊重したいと願っているのである。同じようにして、他者の上に私自身のすがたを見出すのであれば、他者を殺したくない、誰かに殺させたくない。その存在を尊重したいのである。
たとえ戦禍に巻き込まれたとしても、できることならば、殺されていくよりも、殺していくよりも、誰かに殺させていくよりも、どこへでも逃げ出して生き延びたいと願っている。それは、誰も皆、一人一人、仏法がはたらく器であると信じるからなのだろうか。
いま現在、ロシアによるウクライナ侵攻に端を発する戦争の惨状を、映像で目の当たりにしている。周辺国の脅威とも相まって、日本でも武器保有、防衛費の問題が急展開してしまっている感じがする。「敵基地攻撃能力(反撃能力)」という言葉が象徴しているように、「敵」という文字が露骨に表れるようになってきている。敵と見なされたものは、当然、警戒心、不信感を抱くに違いない。それは結局、お互いを尊重して協力し助け合うような関わり合いを放棄するという方向になるのではないか。ここにきて、守るための戦いを正当化することは、極めて危険だと感じている。日本は、かつての戦争を通して、大空襲や原爆投下による被害の悲惨、苦痛、そして加害性について、身をもって知ってきたのだから、同じあやまちを繰り返してしまわないように、メッセージを発信し続けていくべきだと考える。被害の側、加害の側、どちらにもならないように模索するということがあって然るべきだと思うのである。
仏教が重んじる精神は「不害」であると聞いてきた。私自身の在り方を振り返れば、前述した通り、それを実行できてはいない。背いてばかりであると言わざるを得ない。しかし、その精神には賛同したい。誰も、傷つけない、傷つかない解決の道がある。それを探求していったのが、少年悉多太子の仏に成る歩みではなかったか。
一切の苦悩する衆生を摂め取って捨てないと誓う、本願の光に照らされて、自己中心的に分別する、執着する心の否定をくぐる。阿弥陀如来の大いなる慈悲・浄土の光に包まれて、存在の本来性に帰る。「一つである」という道理にまっすぐ順い、現実の「食み合う」世界に責任を取って生きる。それは、本願の名号・南無阿弥陀仏という呼びかけを聞く、信心をいただくというところに帰着する。
尊ぶべきは法である。本当に守るべきものを明らかにしたいと思った次第である。
(2023年3月1日)
最近の投稿を読む…
続きを読む
No posts found
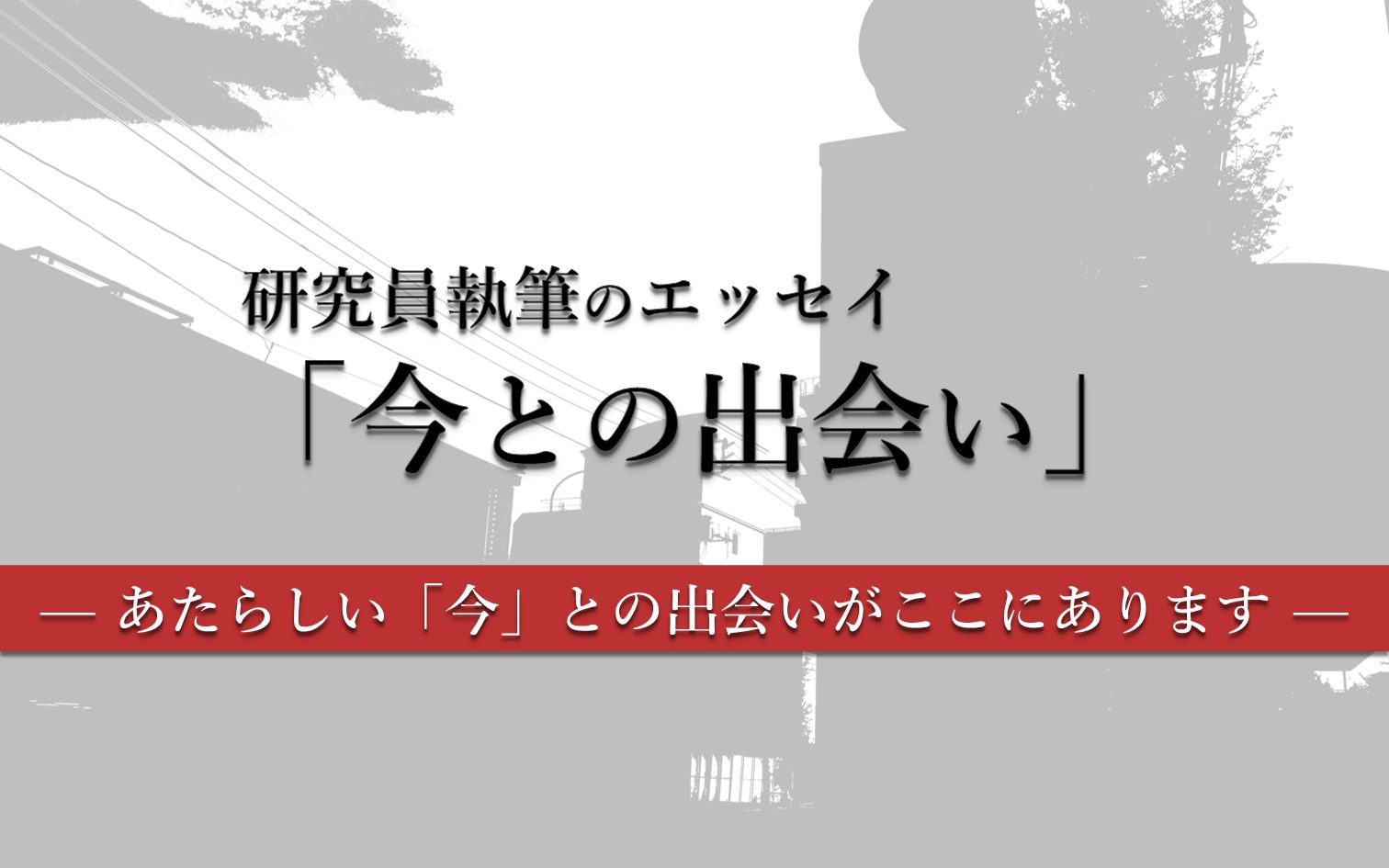
著者別アーカイブ
Menu
