
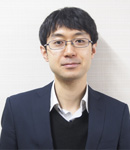
親鸞仏教センター研究員
青柳 英司
(AOYAGI Eishi)
学問は歴史を重ねるに連れ、専門性が高まる傾向にある。
少数の人間のなかでしか問題にならない学問なら、どれほど特殊な用語が増えようと、いかに奇妙な議論が展開されようと、必ずしも問題ではないだろう。しかし、仏教・真宗というものは、多くの人に共有されることを願いとしたものである。にもかかわらず、真宗の教学が内向きになり、公開性を失うのであれば、それは教学としての意義を失うことになりはしないか? そう思わされたのが、今年1月に小山聡子氏から上梓(じょうし)された、『浄土真宗とは何か 親鸞の教えとその系譜』(中公新書)だった。
著者は歴史学の専門家であり、従来の親鸞像が宗祖として理想化されたものであると指摘する。そのうえで、本書は当時の資料から、「等身大の親鸞」や家族・後継者の信仰に迫っている。この試み自体は、極めて重要なものだろう。ただ親鸞の信仰を探るのであれば、その著作が最も有力な「当時の資料」となる。しかし小山氏は、親鸞の著作を十分には読み込んでおられないように思う。
ここでは1点だけ取り上げ、訂正させていただきたい。
親鸞は愚の自覚の困難さについて、少なくとも現存する著作の中では触れていない。自力から他力へと移行するには、その前提として愚の自覚が必要となるはずである。厳しい自己凝視、あるいは自己否定を必要とする他力信心の獲得は、多くの人間には容易でない。
(小山氏前掲書 263頁)
ここで氏は「愚の自覚」を、「自力から他力へと移行する」前提として位置づけている。しかしこれは、親鸞の思想ではない。小山氏の言う「愚の自覚」とは、煩悩(ぼんのう)の尽きない凡夫であるという自覚であろうが、これこそが実は、「真実信心」の内容なのである。たとえば『教行信証』の「信巻」では、『集諸経礼懺儀(らいさんぎ)』を引いて次のように述べられている。
二つには深心、すなわちこれ真実の信心なり。自身はこれ煩悩を具足せる凡夫、善根(ぜんごん)薄少にして三界に流転(るてん)して火宅(かたく)を出でずと信知す。今、弥陀の本弘誓願(ほんぐぜいがん)は、名号を称すること下至十声聞等(げしじっしょうもんとう)に及ぶまで、定んで往生を得しむと信知して、一念に至るに及ぶまで、疑心あることなし。かるがゆえに「深心」と名づく、と。
(『真宗聖典』222頁)
このように「真実の信心」とは、「深心」である。それは「煩悩を具足せる凡夫」であると「信知」することであり、同時に「弥陀の本弘誓願」による往生を「信知」することであると示されている。つまり、「凡夫」であるという自覚は「真実信心」の内容なのであり、他力に移行するための前提ではない。そして親鸞は、この「真実信心」が「難信」であることを、さまざまな著作のなかで繰り返し言及している。よって「親鸞は愚の自覚の困難さについて、少なくとも現存する著作の中では触れていない」というのは、小山氏の誤解である。
真宗教学のなかでは、「愚の自覚」が真実信心であることは常識中の常識である。しかし、氏の「参考文献一覧」には、親鸞の思想に関するものがまったく挙げられていなかった。「浄土真宗とは何か」を論じる場合でも、教学の成果を参照する必要は無いと、見なされてしまったのだろう。もしそうであるなら現在の教学も、「宗門が理想化した親鸞」の思想を扱うものだと、理解されているということだろうか。これはわれわれに突き付けられた、大きな問題であると思う。
教学の常識に立って小山氏の著作を批判することは、決して難しくない。しかし、それよりもわれわれは、現在の研究が本当に普遍性をもったものであるかを検証し、より広く公開する必要があることを痛感した。この点から見れば、氏の著作は良著である。
(2017年5月1日)
