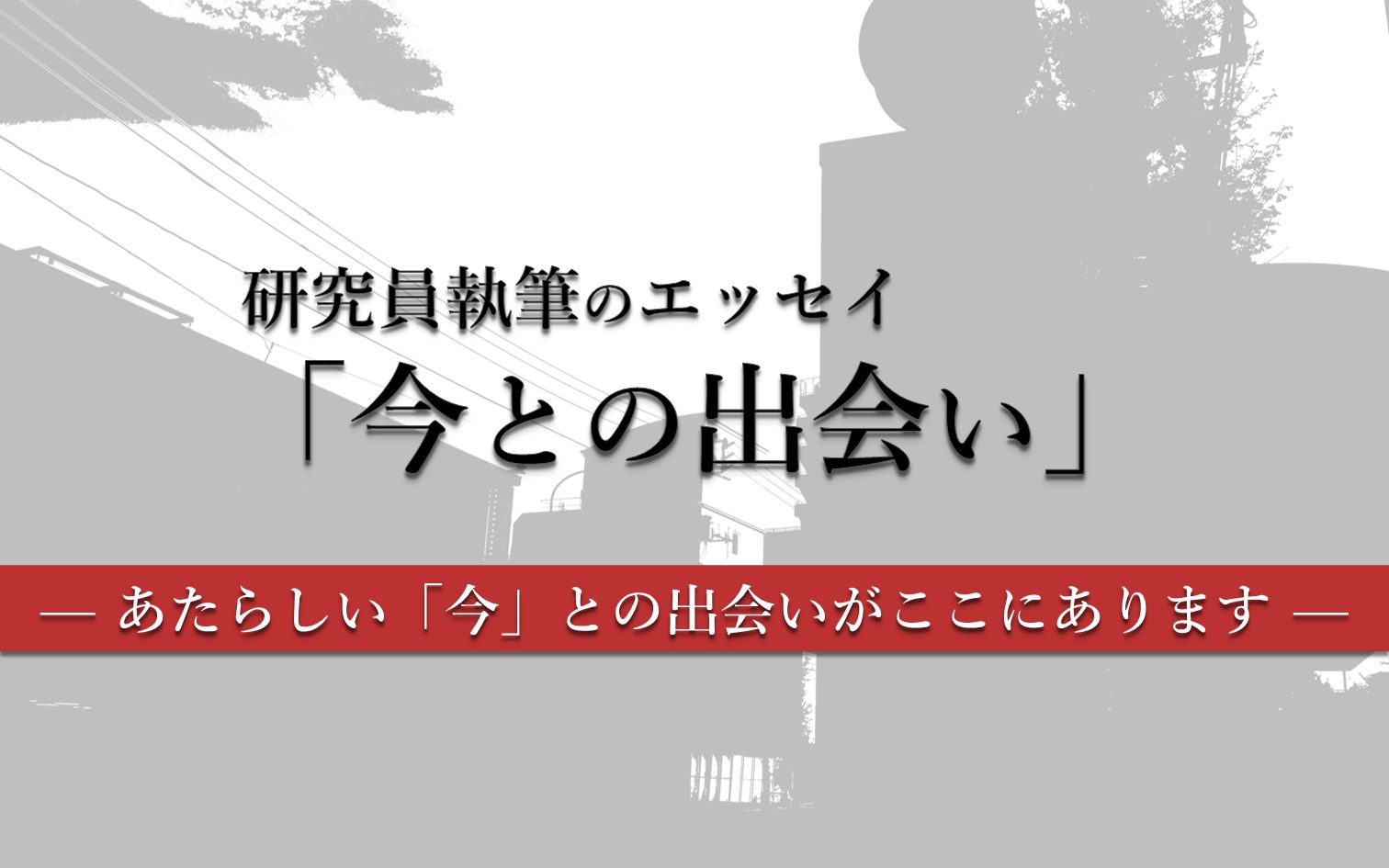今との出会い 第171回「無知を「批判」的に自覚する契機―「浪人」ということについて―」

親鸞仏教センター嘱託研究員
飯島 孝良
(IIJIMA Takayoshi)
先日、ある予備校が主催するセミナーで短い講演をする機会を頂戴した。百数十人を収容する教室を一杯にしたのは、最高レベルの理系学部や医学部を志望する浪人生の皆さんだった。少子化のあおりで浪人生は減少の一途といわれるが、専門性の高い医学部と芸術学部は例外である。
じつは、自分自身「予備校」という空間には浅からぬ思い入れがある。入試でつまずき、自らの無知と無力に直面させられ、絶対に合格するという保証がないなかでも歯を食いしばって鍛錬を重ねる日々――そう書き連ねるといかにも辛そうに思われるかもしれないが、自分のなかには独特な解放感もあった。担うべきものもなく、ただただ貪欲に知を吸収しようとしていたのである。毎日ひたすら問題に打ち込めばよいというのは、考えてみれば贅沢なことなのだった。そして、「将来的には日本の思想史を学んでみたい」という思いが湧きたち、一休や白隠や親鸞といった存在に改めて気づかされたのも、まさにこの浪人時代であった。
予備校という空間で学んだことは多々あるが、何より深く思い知らされたことは、「己に批判的でなければならない」ということであった。「批判」とは罵詈雑言を並べ立てることではなく、主観を排して実体を客観的に冷静に捉えるということである――「発見するうえで最大の障害となるのは無知ではなく、知っていると錯覚することなのである(The greatest obstacle to discovery is not ignorance ―― it is the illusion of knowledge.)」という、米国の歴史家であるダニエル・J・ブーアスティン(Daniel Joseph Boorstin)のことばに深い感銘を受けたのは、入試英語を通してである。その後、今度は自分が高校生や浪人生を相手に入試英語を講じる立場になってからも、繰り返し強調するのは「己に批判的でなければならない」ということであった。そしてそれは、他ならぬ自分自身への戒めであり続けている。
ものを知り、理解が進むと、あたかも世界と歴史と人間のあらゆることがわかりきったような錯覚がもたらされるかもしれない。卓抜した知性を有していればいるほど、その度合いは強くもなろう。しかし、その錯覚が最終的には度し難いエリート意識につながり、人間を思いあがらせてしまうものとなったら、どうだろうか。更に言えば、生と死という最も根本的な問いを「知り尽くす」などということが、原理的にあり得るだろうか。そう考えれば、「浪人」という、一見すれば社会全体から切り捨てられたかのような気にせられる体験は、決して無駄なものではないはずである。むしろ、「自分が何もかも知っている」などと思いあがるような「恥ずべき無知(アマルティア)」(『ソクラテスの弁明』)を「批判」的に自覚する契機として、「浪人」という時代と予備校という空間があってもいいのではないか。いや、まだ何ものでもない「浪人」という在り方こそ、自己を「批判」的にみつめるきっかけを与えてくれるにちがいない――教室一杯に参集してくださった浪人生を前に、かつての予備校生から伝えたかったのはこういう思いである。
これから医者になり、行政のトップになり、それこそ世の羨むようなエリートになろうとする方々を前に、「無知こそ重要」などと語りかけるのは、いささか場違いのようにも思われるだろうか。そうではなく、こういう自らの無知や傲慢を批判的に見つめ続けることには、知性や年齢や地位などに関わらないきわめて普遍的な問題と思えてならない。
***
当日、そうした思いを提示するうえで用いたのは、ふたつの資料である。ひとつは「重力がどのように発見されたか」について、アリストテレス~中世アラブ思想からスコラ哲学~ルネサンスと科学革命に到る変遷を取り上げた英語長文問題である。科学的発見が、人類の無知の自覚に端を発することを見つめてもらおうと考えてのことである。もうひとつ話題に出したのは、一休の頂相(ちんそう。肖像画)である。この奈良国立博物館に所蔵の頂相は五十代半ばの姿とされるが、この時期の一休は既成権力たる禅門から距離を置いて鋭い言句をぶつけ続けていた。ともすれば「とんち小僧」のイメージに限定されがちな一休には、じつは破天荒で複雑な内実もあったのである。そして、そこにある「批判」の精神は、そのまま「自分はその批判に足る禅者なのか」という自省をもたらすものでもあった。そうした在り方こそ、ひとつの「浪人」なのではないのだろうか。「浪人」は、現代ならば大学入試に留まらない普遍的な精神性ともなり得るのでは――そんな思いも腹の底に据えて、浪人生の皆さんへお話をした。
科学知の形成過程にせよ、一休の「像」にせよ、われわれがそれらに触れるうえで最大の障害は「知っていると錯覚すること」に他ならないのである。与えられた時間の枠内で語ったなかから、「批判」の精神をめぐるメッセージが少しでも伝わっていてくれればよいのだが。
※『ソクラテスの弁明』(納富信留訳)については、名和達宜元研究員によるブックレビューがある。
(2017年8月1日)
最近の投稿を読む

今との出会い第233回「8月半ば、韓国・ソウルを訪れて」
2022年10月03日
今との出会い第233回「8月半ば、韓国・ソウルを訪れて」 親鸞仏教センター嘱託研究員 伊藤 真 (ITO Makoto) 8月のお盆休み中、学会発表のために韓国・ソウルを訪れた。海外へ渡航するのも、「リモート」でなく「対面」で学術大会に参加するのも、コロナ禍以来初めてだから実に3年ぶり。ビザの申請に韓国領事館前で炎天下に3時間並び、渡航前・ソウル到着時・帰国前と1週間で3度の規定のPCR検査に緊張し、日韓双方のアプリの登録や電子証明取得など、渡航は苦労の連続だったが、それだけの甲斐はあったと思う。今回は韓国で体験したさまざまな「出会い」について書いてみたい。…
続きを読む
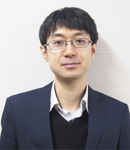
今との出会い 第232回「漫画の中の南無阿弥陀仏」
2022年9月09日
今との出会い 第232回「漫画の中の南無阿弥陀仏」 親鸞仏教センター嘱託研究員 青柳 英司 (AOYAGI Eishi) 日本の仏教史において、南無阿弥陀仏という言葉が持った意味は極めて重い。 この六字の中に、法然は阿弥陀仏の「平等の慈悲」を発見し、親鸞は一切衆生を「招喚」する如来の「勅命」を聞いた。彼らの教えは、身分を越えて様々な人の支援を受け、多くの念仏者を生み出すことになる。そして、現代においても南無阿弥陀仏という言葉は僧侶だけが知る特殊な用語ではない。一般的な国語辞典にも載っており、広く人口に膾炙(かいしゃ)したものであると言える。…
続きを読む

今との出会い 第231回「病に応じて薬を授く」
2022年8月01日
今との出会い 第231回「病に応じて薬を授く」 親鸞仏教センター主任研究員 加来 雄之 (KAKU Takeshi) 「また次に善男子、仏および菩薩を大医とするがゆえに、「善知識」と名づく。何をもってのゆえに。病を知りて薬を知る、病に応じて薬を授くるがゆえに。」(『教行信証』化身土巻、『真宗聖典』354頁)…
続きを読む

今との出会い 第230回「本願成就の「場」」
2022年6月01日
今との出会い 第230回「本願成就の「場」」 親鸞仏教センター嘱託研究員 中村 玲太 (NAKAMURA Ryota) 「信仰を得たら何が変わりますか?」――訊ねられる毎に苦悶する難問であり、断続的に考えている問題である。これは自身の研究課題とする西山義祖・證空(1177…
続きを読む
No posts found