
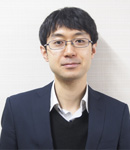
親鸞仏教センター研究員
青柳 英司
(AOYAGI Eishi)
近年のゲームは、コンピュータを相手にするのが一般的だ。
けれど非電子型のテーブルゲーム(俗に言うアナログゲーム)も、決して馴染(なじ)みがなくなったわけではない。たとえば囲碁や将棋、麻雀などは幅広い年齢層に楽しまれているし、トランプや双六(すごろく)、『人生ゲーム』(タカラトミー社)なども、遊んだ経験がある人は多いだろう。
しかし近年、ドイツを震源として、まったく新しいボードゲームが次々に生み出されていることは、あまり知られていない。
その先駆けとなったのが、1995年に発売された『カタンの開拓者たち』(Die Siedler von Catan、コスモス社)だ。これは未開の島の開発をモチーフにしたゲームだが、プレイヤーの選択肢が極めて広い。交易路を長く延ばすもよし、たくさんの都市を築くもよし。あるいは盗賊を利用して、他のプレイヤーの妨害をすることもできる。この独特なゲームシステムは大人でも十分に楽しむことができ―むしろ小さな子どもには難しい―、世界中で高い評価を受けた。
また、ドイツ産のボードゲームには、この他にも斬新なものが多い。そのため日本でも今、これらに触発されるかたちで、さまざまなボードゲームが新たに開発されている。しかもそのなかには、仏教を題材にしたものが少なくない。
その代表は、第1回東京ドイツゲーム大賞を受賞した『枯山水』(2014年、New Games Order,LLC)だろう。「枯山水」は禅宗のなかで発達した庭園様式で、水を使わず、石や砂だけで山水の風景を表現したものだ。このゲームでもプレイヤーは、枯山水の造営を通して禅の精神を表わすことを目指す。そのため各プレイヤーは自分の手番に、「庭をいじる」だけではなく「座禅をする」という選択肢を採ることができる。単に砂を引いていくだけでは、美しい庭は造れない。禅の精神を表わす洗練された枯山水を造るためには、参禅することが必須となるゲームシステムになっているのだ。
もちろん、『枯山水』をプレイしても、禅宗の教えに直接触れられるわけではない。しかし、禅の雰囲気に触れるきっかけにはなるものだろう。
次に紹介する『曼荼羅(まんだら)』(2015年、New Games Order,LLC)も、東京ドイツゲーム賞で特別賞を受賞したものである。プレイヤーは曼荼羅―仏教的宇宙観を表現した絵画―を描く絵師となり、より広大な仏の世界を表わすことを目指す。ただ、そのために必要なのは座禅や瞑想(めいそう)ではなく、六道(地獄・餓鬼・畜生・阿修羅・人・天)を経廻(へめぐ)ることである。広大な仏の世界を表現するためには、六道の苦海に深く沈潜することが必須の条件になっているのだ。
衆生の苦と隔絶したところに仏の世界があるのではなく、苦の衆生を見そなわし、包んでいく存在こそ仏陀である。このような仏教観が、『曼荼羅』のゲームシステムには表現されているように思う。
ただ筆者は寡聞(かぶん)にして、これらのゲームの作者がどのような方かを存じあげない。
しかし現在、僧侶の側にもボードゲームを通じて仏教を発信しようとする試みがある。その第一人者が、臨済宗妙心寺派陽岳寺の副住職、向井真人(むかい まひと)氏だ。氏はすでに『御朱印集め』や『檀家―DANKA―』、『WAになって語ろう』などの作品を世に出している。これらは教義を解説するためのものではなく、あくまでも僧侶や寺院、仏教のある生活が、身近に感じられることを目指したものである。またゲームと言っても、子どもだけを対象としたものではない。大人も充分に楽しむことができる洗練されたものとなっている。
さらに向井氏は現在、江戸時代に作られた「浄土双六」を現代風にアレンジし、仏教的世界観をペーパークラフトで立体的に表現したゲームを開発中だ。こちらは仏教の基本的な考え方に、触れることができるものになるだろう。
もちろん、仏教をゲーム化することに、抵抗のある人もいるかもしれない。しかし、寺院や仏教は敷居が高いと言われて久しいのも事実である。従来とは異なる仏教の発信方法を、積極的に模索していく必要があることは間違いない。その点でボードゲーム化という試みは、新しい仏教の表現・伝達方法を切り開くものだと言えるだろう。
(2018年3月1日)
