
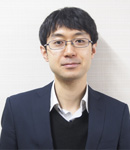
親鸞仏教センター研究員
青柳 英司
(AOYAGI Eishi)
ハイル=ベイという人物のことが、何となく気になっている。
彼はマムルーク朝の軍人で、16世紀の初頭にはシリアの大都市アレッポの太守(たいしゅ)を務めていた。一般的には、おそらく無名の人物だろう。
そもそも、ハイル=ベイが仕えたマムルーク朝のことすら、日本ではあまり話題にならない。そこで少し遠回りになるが、その辺りのことから話を始めてみたい。
マムルーク朝の「マムルーク」とは、「所有された者」という意味だ。つまりは、奴隷のことである。しかし、単なる奴隷ではなかった。イスラーム世界では10世紀ころから、遊牧民の子弟を買ってきて一流の教育と訓練を与え、優秀な軍人に育てるということが行われてきた。この奴隷身分出身の軍人が「マムルーク」であり、彼らがエジプトとシリアに築いた王国が、マムルーク朝なのである。
この国が中東の歴史に果たした役割は、決して小さくない。彼らはモンゴルの侵略からイスラーム世界を護り、十字軍に奪われたムスリム(イスラーム教徒)の地を取り戻した。これらを成し遂げたマムルーク朝の英主バイバルスは、現在の中東でも極めて人気が高い。
けれどハイル=ベイの生きた時代、その栄光はほとんど過去のものになっていた。宮廷では派閥抗争が繰り返され、官僚も賄賂(わいろ)を求めることが常態化していたという。明らかに民心は、マムルーク朝から離れつつあった。
この状況にハイル=ベイが何を思っていたのか、それはわからない。
ただ彼はマムルーク朝の滅亡に際して、重要な役割を担うことになる。
1516年の8月。
オスマン帝国第9代スルタン(皇帝)のセリム1世が、その矛先をシリアに向けた。
オスマン帝国もマムルーク朝もスンニ派の王朝であり、イスラーム法はムスリム同士の争いを禁じている。しかしセリムは、マムルーク朝がシーア派のサファヴィー朝に接近したことを根拠に、ウラマー(イスラーム法学者)から次のような法判断を取り付けた。
「異端を助ける者は異端である。異端との戦いは、聖戦である」
当時のマムルーク朝は、イスラームの聖地であるメッカとマディーナの守護者であり、スンニ派イスラーム世界の盟主を自認していた。しかしセリムは、マムルーク朝を異端として告発し、その地位を否定したのである。
オスマン帝国とマムルーク朝の会戦は、アレッポにほど近いダービクの平原(マルジュ=ダービク)で行われた。両軍の規模がどの程度であったのかは、よくわからない。しかし両軍を合わせれば、10万を越える兵力になったのは確実だろう。
ただ、蓋(ふた)を開けてみると、戦いはオスマン帝国側の一方的な勝利に終わった。 マムルーク朝の敗因の1つは、明らかに装備の差である。オスマン帝国が早くから鉄砲や大砲を導入していたのに対し、マムルーク朝軍の主力は依然として、弓や槍で戦う騎兵たちだった。日本の長篠の戦いもそうであったように、騎兵の突撃は鉄砲の一斉射撃に勝てない。
そしてもう1つの敗因は、左翼軍を率いていたハイル=ベイの寝返りだった。セリムは彼の内応(ないおう)を取り付けた状態で、会戦に臨んでいたのである。これによってマムルーク朝の敗北は、決定的なものになった。
翌年には首都のカイロも占領され、マムルーク朝は滅亡に追いやられる。
ハイル=ベイは、オスマン帝国の初代エジプト総督へ任じられた。
では、彼は玉座を奪い取るために、祖国を裏切ったのだろうか。
そのように見ることは、もちろん簡単である。
けれど彼はセリムが帰国し、急死した後も、独立を試みようとはしなかった。それどころか率先してオスマン帝国の官服を身に着け、オスマン帝国の諸制度を導入し、マムルーク朝のものを排除していく。
ハイル=ベイの寝返りは、本当に単なる野心の所産だったのだろうか。
疑いが残る。
彼が本当に望んだものとは、何だったのだろうか。
私はそこが、ずっと気になっている。
ただ、祖国を滅ぼしてもよいと思うことが、人間の身の上には起こるのだ。
それだけは、事実である。
(2019年1月1日)
