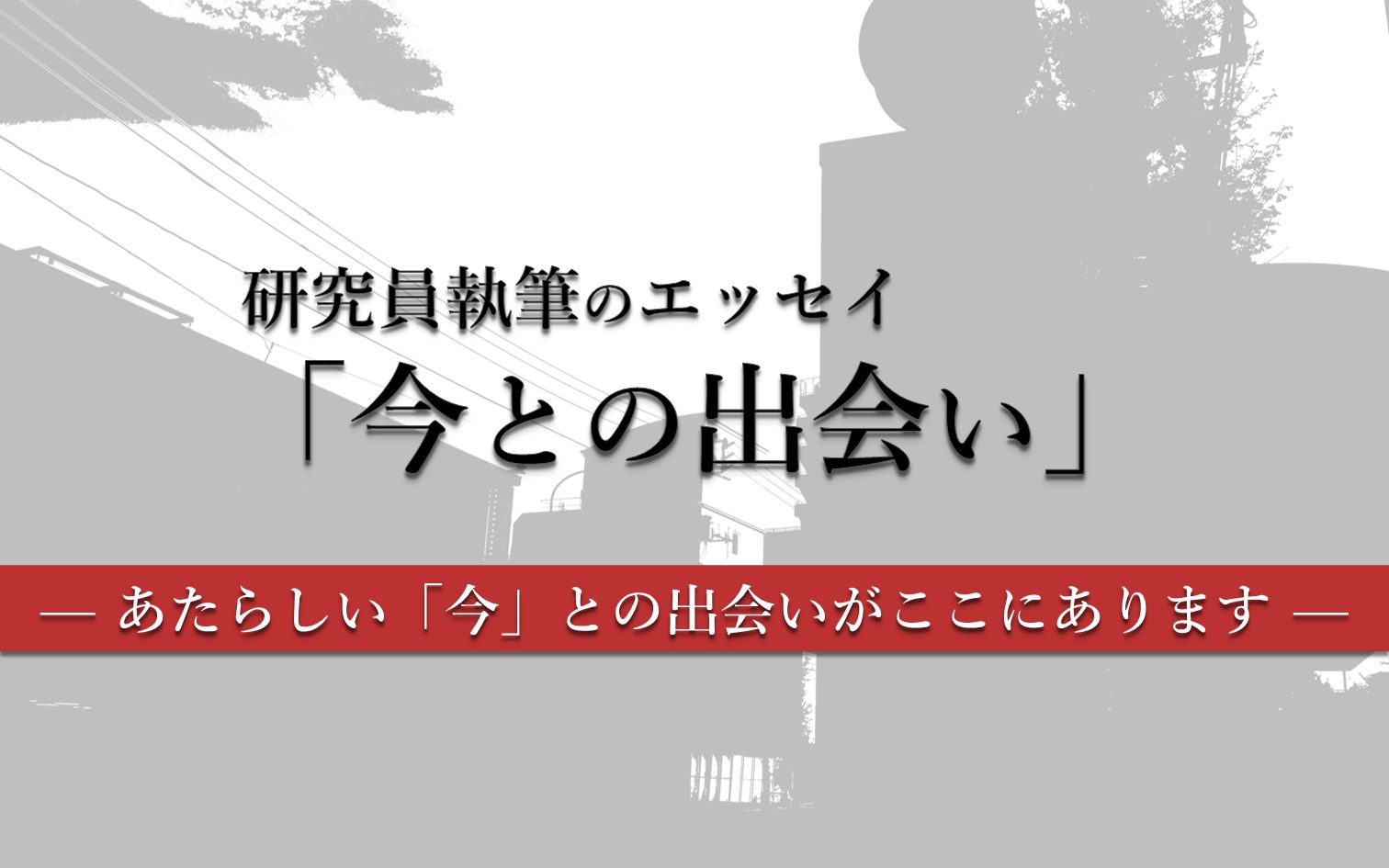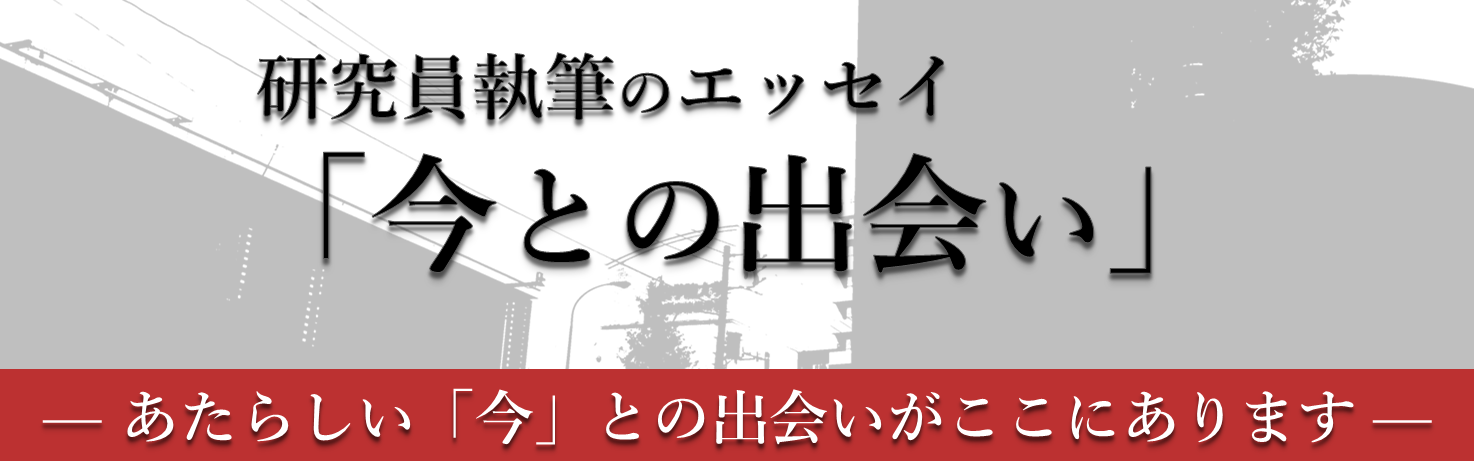
今との出会い第192回「「共感」の危うさ」

親鸞仏教センター嘱託研究員
大谷 一郎
(OTANI Ichiro)
私は、心の悩み相談を受けるカウンセラーという仕事にも少し携わっている。カウンセラーの基本的態度として「傾聴」ということがある。傾聴とは、カウンセラーの価値観や判断にしたがってクライエント(相談者)にアドバイスしたりするのではなく、まずは、クライエントの話をしっかりと聴くことである。そのときのカウンセラーの態度として大事なのが「共感」ということである。クライエントを無条件で受容し、共感的態度で話を聴き、クライエントがどのような基準で物事を見ているのか、何を感じ、それが当人にとってどのような意味をもっているのかということを理解し、クライエントの本当に言いたいことを理解していくのである。共感ということがなければ関係は成立しない。
カウンセリングの場だけにとどまらず、その人の見方、感じ方、考え方に思いをはせ、その人のように感じる「共感」ということは、日本の社会では、一般的に肯定的に受け止められているように思う。確かに共感的理解がなければ、職場でも家庭でも人間関係がギスギスして生きづらいかもしれない。
先日、「ロバートキャンベルさんが語る「共感」の危うさ」(ハフポスト「あの人のことば」2019年3月14日更新)という記事を目にした。キャンベル氏は、まずは、「共に感じる、人の感情を追体験して共振する。共感する素質を育てていくことは人間社会にとっても大切なことです。」と語る。しかし、そこには時に危うさもあることを指摘する。それは、誰かの意見に対して、共感した人たちとそうでない人たちとの間で枠ができてしまい、共感できる人たちは卵の殻のような「共感の硬いシェル」で覆われてしまい、その殻を突き破ることはなかなかできないというのだ。アメリカのトランプ政権の支持者も、トランプ大統領が憲法違反をしても、嘘をついても、人を傷つけても必ず支持率三十数パーセントは動かず、共感の殻の中にいる。つまり「共感」は、社会を分断することもあるのだ。
そこで、キャンベル氏は、ファクト(事実)に基づく理解ということが大切だと言う。例えばLGBTの問題でも、同性婚に対して共感できなくても、当事者が生きるうえでの必要な法整備(緊急時の病院での面会、遺産相続の配偶者控除の問題など)が整っていないという事実に対し、同性婚には共感できないが当事者が生きるための法整備は必要であるという「理解」はできるだろうということだ。
私はここでハンナ・アーレント(Hannah Arendt)のことを思い出した。アーレントは『全体主義の起源』や『エルサレムのアイヒマン』などで、ナチズムやスターリン主義などの全体主義はいかにして起こり、なぜ誰も止められなかったのかということを明らかにしようとしたドイツ系ユダヤ人の政治哲学者だ。アーレントは、深く考えることをせず、自分が共感できるわかりやすい意見を求めることは、全体主義的世界観を支持した大衆の心理だと指摘している。このことは、現在私たちが生きている社会でもいえることではないか。ここにからめとられないためにはどうすればよいのか。アーレントは「複数性に耐える」という概念を言う。「複数性に耐える」とは物事を他者の視線で見るということだと仲正昌樹氏(金沢大学法学類教授)は言う。(仲正昌樹『ハンナ・アーレント全体主義の起源(100分de名著)』NHK出版参照)これは、自分が共感できるような意見をもつ人々との殻の中に閉じこもるのではなく、まさに違う視点から物事を見ていくということだろう。例えば、LGBTは一切受け入れられないというのではなく、当事者の視点「複数性」に立ち「理解」していくということになるのではないか。
カウンセリングでは一対一の関係でより深く内面を理解していくためには共感は不可欠だが、日常の生活において、社会と関わっていくときに、安易な共感とそこでの思考停止に陥らないためにはこの視点が大切になってくるのではないだろうか。
(2019年5月1日)
最近の投稿を読む

今との出会い 第232回「漫画の中の南無阿弥陀仏」
2022年9月09日
今との出会い 第232回「漫画の中の南無阿弥陀仏」 親鸞仏教センター嘱託研究員 青柳 英司 (AOYAGI Eishi) 日本の仏教史において、南無阿弥陀仏という言葉が持った意味は極めて重い。 この六字の中に、法然は阿弥陀仏の「平等の慈悲」を発見し、親鸞は一切衆生を「招喚」する如来の「勅命」を聞いた。彼らの教えは、身分を越えて様々な人の支援を受け、多くの念仏者を生み出すことになる。そして、現代においても南無阿弥陀仏という言葉は僧侶だけが知る特殊な用語ではない。一般的な国語辞典にも載っており、広く人口に膾炙(かいしゃ)したものであると言える。…
続きを読む

今との出会い 第231回「病に応じて薬を授く」
2022年8月01日
今との出会い 第231回「病に応じて薬を授く」 親鸞仏教センター主任研究員 加来 雄之 (KAKU Takeshi) 「また次に善男子、仏および菩薩を大医とするがゆえに、「善知識」と名づく。何をもってのゆえに。病を知りて薬を知る、病に応じて薬を授くるがゆえに。」(『教行信証』化身土巻、『真宗聖典』354頁)…
続きを読む

今との出会い 第230回「本願成就の「場」」
2022年6月01日
今との出会い 第230回「本願成就の「場」」 親鸞仏教センター嘱託研究員 中村 玲太 (NAKAMURA Ryota) 「信仰を得たら何が変わりますか?」――訊ねられる毎に苦悶する難問であり、断続的に考えている問題である。これは自身の研究課題とする西山義祖・證空(1177…
続きを読む

今との出会い 第229回「哲学者とは何者か」
2022年5月01日
今との出会い 第229回「哲学者とは何者か」 親鸞仏教センター嘱託研究員 越部 良一 (KOSHIBE Ryoichi) 今、ヤスパースの『理性と実存』を訳しているので、なぜ自分がこうしたことをしているのかを書いて見よう。…
続きを読む
No posts found