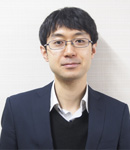今との出会い 200回記念企画「人生における時の厚みと深さ」

親鸞仏教センター所長
本多 弘之
(HONDA Hiroyuki)
現在の日本は、高齢化が進み人口が減少し始めたと言われている。そして、その高齢化社会を支える社会福祉制度が、国家予算の大幅な赤字で危機的状態だともされている。人生がただ長さのみを追求する価値観の流布によって、生命がもたらす老化現象の問題が、さまざまな角度から話題になってもいるのである。
生命とは、生まれると同時に成長し、平衡状態に入り、そして老衰し、死に至る。この必然の生命現象には、しかしながらその過程それぞれに、生命の質の変化があると言えよう。成長過程の経験の蓄積は、濃密であってしかもその記憶は深く記録され、老化現象にも耐えて、いつも思い出されてくるのだと言われる。その反面、老化した人にとってのその時々の出来事は、すぐに忘れられてしまう。
この文章の筆者も、いうまでもなく後期高齢者とされる老境にある。確かに若い頃に習得した語学などは、随分と一心に習ったためもあろうが、結構いまでも記憶に残っている。しかし、近年に必要があって習い始めた外国語などは、情けないことに、覚えた翌日にはもう忘れてしまっている。
金子大榮師から聞いた言葉であったが、「人生は長さのみでなく、深く生きるということがある」というのがあった。この場合の深さは、言うまでもなく宗教的な自覚による人生の味わいを表現しようとするものであろうが、このことを、経験の構造上の深さに当てて考え直してみよう。
生存に取っての時間には、先に述べたように、確かにその生命の状態が成長期か老年期かによって、厚みや深さが異なるのだが、生命にとっての時間の質の根底に、生きる力を支えているような作用があるのではないか。生命存在一般に、その生命力の根源の力のようなものが感じられるとき、その力を与えてくる根源の深さには、生存の深さや厚さを貫いている調整力ともいうべきものが感じられる。
生きていることを成り立たせる力に、力強いこの調整能力があることを、あたかも外の力にその根源があるかのごとく表象的に表現してきたのが、いわば通途の宗教的な言葉の意味なのかもしれない。そうしてみると、親鸞がいう「自然のよう」とは、この根底の大きな力を言い当てる言葉だったとも言えようか。
(2020年2月1日)
最近の投稿を読む

著者別アーカイブ
- 今との出会い第234回「「適当」を選ぶ私」
- 今との出会い 第230回「本願成就の「場」」
- 今との出会い 第222回「仏教伝道の多様化にいかに向き合うか」
- 今との出会い 第221回「「自由」と「服従」」
- 今との出会い 第218回「思惟ということ」
- 今との出会い 第220回「そういう状態」
- 今との出会い 第211回「#Black Lives Matter ――差別から思うこと」
- 今との出会い 第210回「あの時代の憧憬」
- 今との出会い 第207回「浄土の感覚」
- 今との出会い 第202回「「救い」ということ」
- 今との出会い 第200回「そもそも王舎城で―マガダ国王・頻婆娑羅(ビンビサーラ)考―」
- 今との出会い 第199回「曖昧なブラック」
- 今との出会い 第198回「一瞬の同時成立」
- 今との出会い 第196回「ともしびとなる日々」
- 今との出会い 第194回「星の祝祭を手のひらに」
- 今との出会い 第192回「「共感」の危うさ」
- 今との出会い 第190回「再び王舎城へ―阿難最後の願いと第一結集の開催―」
- 今との出会い 第186回「人生、なるようにしか……」
- 今との出会い 第184回「ひとりの夢を」
- 今との出会い 第182回「遺伝性の疾患等の理由で強制不妊手術が行われていたという報道に触れて思うこと」
- 今との出会い 第180回「地涌の菩薩」をどう読むか
- 今との出会い 第176回「自分との対話」
- 今との出会い 第174回「そしてハイシャはつづく」
- 今との出会い 第172回 「劉暁波氏の訃報にふれて思うこと」
- 今との出会い 第170回「現代へのまなざし」
- 今との出会い 第166回「独り立つ「人」」
- 今との出会い 第164回「誰かと生きる時間」
- 今との出会い 第163回「市場経済とペットの命」