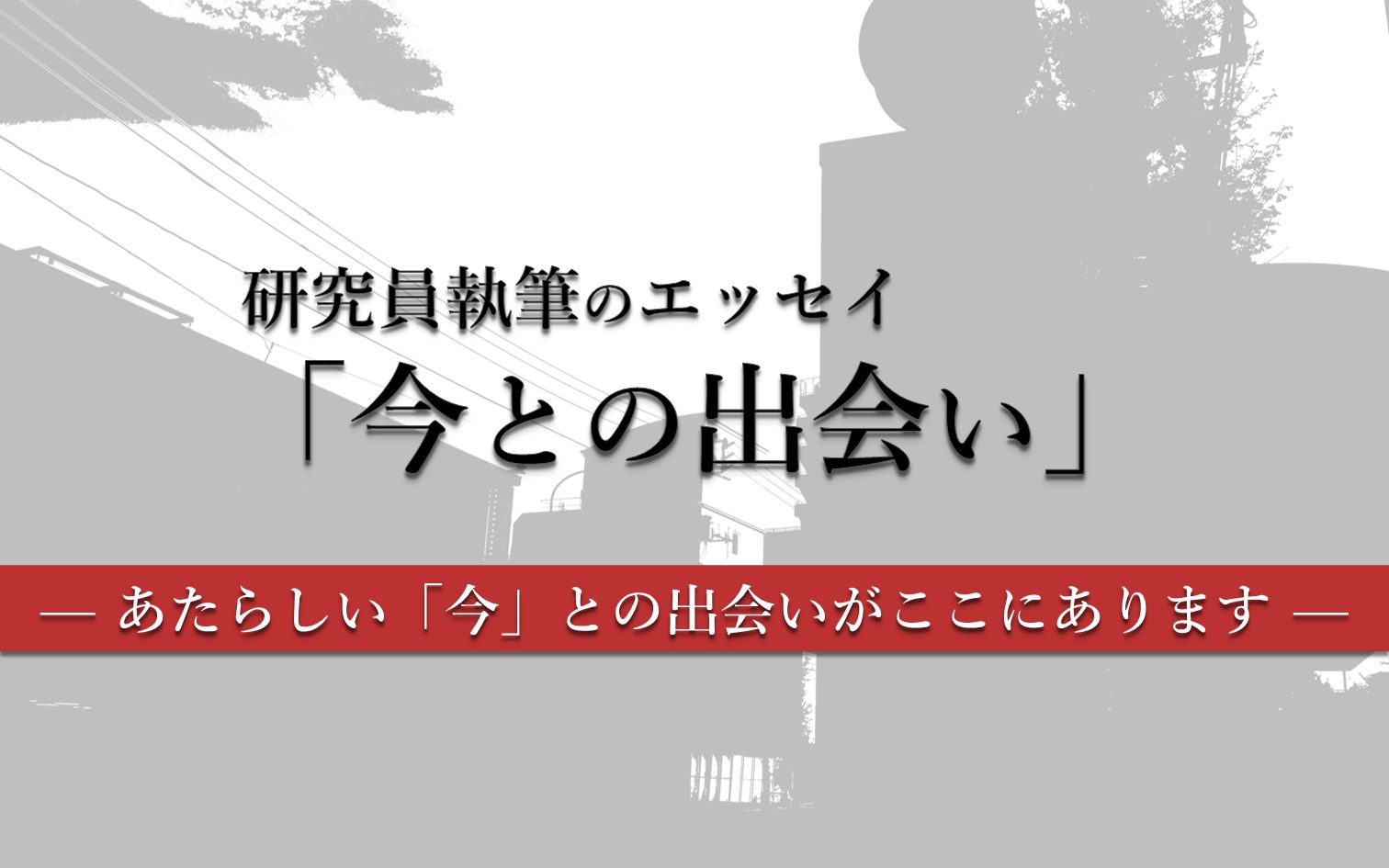今との出会い 第207回「浄土の感覚」

親鸞仏教センター研究員
東 真行
(AZUMA Shingyo)
身辺整理をしている女性がふと、『聖書』とおぼしき古ぼけた書物を手にしているのを目にして、ある少女が問う。あなたは神を信じているの、と。
女性はすこし間を置いてから「信じてるよ」と答える。そして、このように続ける。
信じてるけど… その質問は、あんまり好きじゃない 海を割ったとか 触れただけで病を癒したとか そういうことの真偽の話ではなくて
(西UKO『はんぶんこ』、UKOZ、2019年、25頁)
こんな前置きのあと、みずからの実感について譬喩を用いて語りはじめる。
たとえば、あなたが5歳くらいの子どもであったとしよう。目を覚ますと真っ暗な荒野にただひとり、空腹で、方角も分からぬまま佇んでいるとしたら、そのとき何を拠り所として、みずからを支えるだろう。
誰かがそばにいてくれたら、と思う者もあるにちがいない。場合によっては、子どもはじぶんの親のことを想起するかもしれない。
5歳といわず、もう少し私たち自身の年齢に引き寄せて考えてみよう。暴力や知力、財力など諸々の力がみずからを孤独から守ってくれると思う者もあるだろう。もちろん、ただ慌てふためくだけの者もいるはずだ。
冒頭に記した女性は「私はそういう時、心の中で神様と手を繫いでいる」と語る。「神様は私がここにひとりぼっちでいることをご存じだ」、そう思うと心に安寧が訪れるのだと。そして、こう話を締めくくる――「私の信じてる、は そういう信じてる」。
聖典に説かれる、ありそうもない記述をそのまま受けいれることではなく、寄る辺ない孤独のなかで私と共なってくれる方が必ずいると信じる。ここでいわれているのは、そのような信仰である。
これを読んだときに思い出したのは、また別の、こんな逸話だった。
ひとりのベトナム帰還兵が、ある教会を訪ねたときのことである。かれは以下のように心境を打ち明ける。「牧師様、私には理解できません。神様はなぜ幼い子どもを見殺しにされたのか? この状態、この戦争、このいまいましさは何なのでしょう? 友人は皆死んでしまいました……」。
牧師はこう答えた。「私には分からないんです、戦争に行ったことがないのですから」と。この応答を受けて、兵士は次のように語ったという。
私は言いました。「戦争のことを尋ねたんじゃないんです。神様について尋ねたんですよ」。
(E・F・ロフタス/K・ケッチャム『抑圧された記憶の神話』、仲真紀子訳、誠信書房、2000年、401頁)
ここでは譬喩を介さず、現実そのものを通して神が問われている。なるほど、時間さえも含めた、この世界のすべてを創造したのだから、現実の悩ましい一端を問うことは神の御業を問うことにもなろう。
信仰の内実というのは確かに、私たちの現実認識をはるかに超え出ている。そのため、たとえば譬喩などの助けを借りて、ひとは信仰を語り得るのである。しかし同時に、信仰は実際の現実世界と深く関係しており、ただ個人の心中に幽閉されるだけの出来事ではない。現実を超えながらも、極めて現実的な出来事としてある信仰をいかに語るか。あまたの信仰者を悩ませてきた課題である。
親鸞の主著『顕浄土真実教行証文類』(『教行信証』信巻)にはこのような言葉がある。
しかるに『経』に「聞」と言うは、衆生、仏願の生起・本末を聞きて疑心あることなし。
(『真宗聖典』、東本願寺出版、1978年、240頁)
経典中の「聞」という言葉の注釈を端緒に、ふたごころなく一心に教説を聞きいれることを「信心」として述べていく箇所であり、親鸞みずからの信仰を最も端的に表現する文章のひとつといえるだろう。昔も昔、はるか大昔に法蔵菩薩が誓願を成就して阿弥陀仏となった、という物語を疑いなしにまっすぐ受けとめる。そういう信仰が語られている。
その阿弥陀仏が在します世界こそ浄土であり、私たちの世界から遠く離れて西方に実在すると説かれている。教説を文字通り受けとめるならば、おどろくべきことに浄土はこの現実世界上、実際に存在するのである。
ところで、脚本家・映画監督の高橋洋は地獄について、このように記している。
どんなときに地獄を感じ取るかと言えば、言うまでもない、地中奥深くに潜む地獄そのものと繫がったと感じたときである。
(「地獄の感覚」『アンジャリ』第39号所収、親鸞仏教センター、2020年、4頁)
高橋にとって地獄とは「どこか現世とは次元の異なる空間に抽象的に想起されるものではなく、自分の足元、地下数十キロだか数百キロを果てしなくボーリングしていけばボコッと空洞に行き当たるかのように地続きに実在する」のであり、「そういう感覚がずっと昔からある」のだという。かれはこのような地獄についての感覚を神代辰巳監督・田中陽造脚本の傑作『地獄』(東映、1979年)をもとに、垂直的な「繫がりの感覚」と述べている。
ひるがえって考えてみると経典に説かれる浄土とは、私たちと十万億の仏土を隔てる遠き彼方にありながらも、水平的な「繫がりの感覚」を拠り所として、字面のごとく地続きに実在する世界である。
この水平の感覚については、安田理深(『名号があって机があれば』、日月文庫、2016年)がすでに指摘しており、四方田犬彦が『親鸞への接近』(工作舎、2018年)において『教行信証』の文体から読み解いているのも同様の感覚、または世界観であろう。先述した『地獄』の終幕では、まるですべての罪悪を超えるかのように、赤ん坊が海の彼方から飛来してくるが、見事な水平感覚の表現である。
「手を繫いでいる」または「繫がりの感覚」といった表現は、「関係している」「はたらいている」などという言葉よりもずっと強く、実感と共に私たちの心身に肉迫してくる。そして、これらの表現は「それは譬喩である」という留保を、少なくともしばらくは寄せつけない。そればかりか、たとえば弾圧などの危機的な状況下においては特に留保や改変を許さないだろう。そういった強い表現を、金子大榮はかつて物語と呼称した。
物語は、実際の通りである必要はない。しかし、だからと言って虚偽ではなく、または単に何かの譬喩として代替されない。方便として真実を指し示すことはあっても、物語とはもっとゆたかな圧縮された表現である。
この世界のはるか彼方に浄土がある。この物語を聞く現在の私たちの実感とは――金子が『浄土の観念』(文栄堂、1925年)でそのことを問うてから、あと数年で100年を経過する。
(2020年7月1日)
最近の投稿を読む

今との出会い 第231回「病に応じて薬を授く」
2022年8月01日
今との出会い 第231回「病に応じて薬を授く」 親鸞仏教センター主任研究員 加来 雄之 (KAKU Takeshi) 「また次に善男子、仏および菩薩を大医とするがゆえに、「善知識」と名づく。何をもってのゆえに。病を知りて薬を知る、病に応じて薬を授くるがゆえに。」(『教行信証』化身土巻、『真宗聖典』354頁)…
続きを読む

今との出会い 第230回「本願成就の「場」」
2022年6月01日
今との出会い 第230回「本願成就の「場」」 親鸞仏教センター嘱託研究員 中村 玲太 (NAKAMURA Ryota) 「信仰を得たら何が変わりますか?」――訊ねられる毎に苦悶する難問であり、断続的に考えている問題である。これは自身の研究課題とする西山義祖・證空(1177…
続きを読む

今との出会い 第229回「哲学者とは何者か」
2022年5月01日
今との出会い 第229回「哲学者とは何者か」 親鸞仏教センター嘱託研究員 越部 良一 (KOSHIBE Ryoichi) 今、ヤスパースの『理性と実存』を訳しているので、なぜ自分がこうしたことをしているのかを書いて見よう。…
続きを読む

今との出会い 第228回「喪失の「永遠のあとまわし」―『トロピカル〜ジュ!プリキュア』論―」
2022年4月01日
今との出会い 第228回「喪失の「永遠のあとまわし」―『トロピカル〜ジュ!プリキュア』論―」 親鸞仏教センター嘱託研究員 長谷川 琢哉 (HASEGAWA Takuya) 娘が4歳になって幼稚園に通うようになると、プリキュアを見るようになった。それまでは恐竜や妖怪の人形でおままごとをしていた娘が幼稚園の友達の影響でプリキュアを見るようなったことに対しては、感慨とともに若干の寂しさを覚えたが、私が日曜朝の『トロピカル~ジュ!プリキュア』(以下、『トロプリ』。ABCテレビ・テレビ朝日系列にて放送)を娘と一緒に楽しみにするようになるまでほとんど時間はかからなかった。…
続きを読む
No posts found