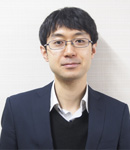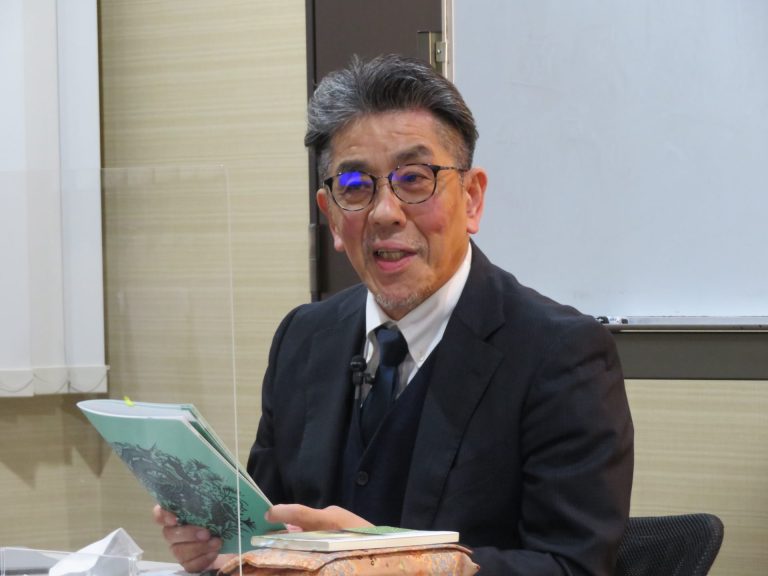研究員執筆のエッセイ
今との出会い
あたらしい「今」との出会いがここにあります
今との出会い第247回「表現の「自由」の哲学的意味」

親鸞仏教センター嘱託研究員
越部 良一
(KOSHIBE Ryoichi)
「自由」は正反対の二つの意味をもつ。これをプラトンの言う魂の三部分で表現すれば、一つは魂の欲望部分の自由。もう一つは魂の理知の部分の自由、これは魂の知るはたらきが、感覚世界を超え、人間を超えた永遠の善美のイデアと結びつき、欲望部分(金銭欲で代表される)と気概の部分(勝利を求める)による囚われから解放されることである。これが自由の真実の意味である(前者は欲望への隷属)。
私に思うに、この真実義中の、思想・文学・芸術およびそれらに類するものの表現(以下、単に表現と記す)の自由には、三つの面がある。
一つ。法然が流罪にされる折、
「一人の弟子に対して一向専念の義をのべたまう。西阿弥陀仏という弟子推参していわく、かくのごときの御義ゆめゆめあるべからず候。[中略]上人のたまわく、汝、経釈の文をみずや。西阿がいわく、経釈の文はしかりといえども、世間の機嫌を存ずるばかりなり。上人のたまわく、我首をきらるとも、此事いわずはあるべからず」(「法然上人伝絵詞(琳阿本)」、井川定慶編『法然上人伝全集』。但し、漢字、かなは現行のものに直し、一部漢字はひらがなにしている。引用文中の[ ]内は越部注記、以下同様)。
表現の自由は、世間に囚われず、煩悩の命に縛られない。
二つ。小林秀雄は本居宣長の「神」についてこう述べる。
「何度言ってもいい事だが、彼[本居宣長]は、神につき、要するに、「何にまれ、尋常(よのつね)ならずすぐれたる徳(こと)のありて、可畏(かしこ)き物を迦微(かみ)とは云なり」と言い、やかましい定義めいた事など、一切言わなかった。[中略]神は、[上古の]人々めいめいの個性なり力量なりに応じて、素直に経験されていたまでだ。そこで勢い、いろいろな神々が姿を現すことになったわけだが、そのような事を、特に意識に上す人はなかったのである。誰の心にも、「私」はなく、ただ、「可畏き物」に向い、どういう態度を取り、これをどう迎えようかという想いで、一ぱいだったからだ。言い代えれば、測り知れぬ物に、どう仕様もなく、捕えられていたからだ」(『本居宣長(下)』新潮文庫)。「神々は、彼等[上古の人々]を信じ、その驚くべき心を、彼等に通わせ、君達の、信ずるところを語れ、という様子を見せたであろう」(同上)。
表現の自由は、いろいろな個性、いろいろな真実、いろいろな善に対し開かれている。
三つ。ヤスパースは、プラトンの国家による検閲の考えを批判して言う。
「プラトンにより考えられた検閲[イデアを知り尽くした哲人王による文学、音楽等の検閲]を、人間は遂行する能力はない。こうした検閲は、繰り返し教会の、そして国家の権力者たちにより得ようと努められるが、退けられてしかるべきである。[中略]強制の圧迫のもとでは、精神は、反復したり変奏したりすることはできるが、創造的に産み出すことはできない。検閲は、ばかげたことと共に真理の可能性をも同時に窒息させ、雑草と共に穀物をも同時に根こそぎにするであろう。だから各々の人間が、自由な産出の権利をもたねばならない」(『原爆と、人間の将来』、原書から越部訳)。
表現の自由は、有限な人間にとって、悪しき表現を乗り越える動きの中にしかないのだから、悪しき表現をつねに目にとどめていなければならない。それは悪しき表現に批判的に対峙するが、しかし、強制なしにである。
善美と真実の根源たるかの無限のもの、測り知れぬものは、個の人をとらえ、個の人を感動させる。自由とは、自己でないかのものに、自己が由るということである。そこで初めて本当の自己(真実の自己存在、実存)が明らかになる。だから自らの表現の自由を抑圧するのは他の者だけでない。根本的には、命濁(みょうじょく)の自分が抑圧し(上の第一面に反す)、自己の真理の根源がもつ多様な可能性を認められぬ自分が抑圧し(第二面に反す)、自己の悪しき面を見まいとする自分が抑圧するのである(第三面に反す)。
かのものが語れという様子を見せるということは、人間関係の中で生きておれという様子を見せるということでもある。かのものは人間たちを結びつける。かの無限者が、特定のとき・ところで、有限な様々な姿形(すがたかたち)のうちに現象し、表現される際、そこで結びつけられる人間たちは限定された人たちである。その表現の根源たる、姿形なき、言葉で語り得ぬ、不可思議なるものとしては、かのものは、一切の存在を、それゆえあらゆる人間をも越え包む、一なるものと思考されうる。
表現の自由のかたき役に、人間たちの客観的な結びつき、集合体を表す「社会」がなることがあるのは、自由な表現と沈黙の出どころである超越者と実存の関係、社会を超出するこの関係を、社会が見失うことがあるからである。キルケゴールは言う。
「社会性という、現代において偶像化されている積極的な原理こそ、人心を腐蝕するもの、退廃させるものであり、だから人々は反省[情熱なき分別]の奴隷となって美徳[例えば命がけの勇敢さ]をさえ輝かしい悪徳にしてしまう。こういう事態になるというのも、個人個人が宗教的な意味で永遠の責任を負って、ひとりひとり別々に神の前に立っているということが見のがされているからのことでなくてなんであろう」(『現代の批判』桝田啓三郎訳、岩波文庫)。
人間が社会なしに存在しないからといって、社会自体の位階と分限を曖昧にすべきでない。魚が水なしで生きられないからといって、魚は水ではないし、水だけで生きているのでもなく、水のために生きていると言えるわけでもない。社会は自由を根底とすべきものであり、又、自由の可能性に奉仕すべきものだ。社会のこの位置づけと社会的責務が見失われ、社会が玉座にすわれば、表現の自由は消失する。
この文章の出だしですでに、私(越部)の内部に表現の自由などありはしないのだということがよく分かる。あるのは囚われである。しかし、それで済みはしないのは、かの剛毅な、独立自由の人たちが呼びかける、そう、社会の内で呼びかける、その表現が、私の心の内に入り込んで来るからである。だから私は、パティ・スミスにならって、こう言うのだ、
「社会の外側で、かの人たちが私を待ち受けている」。“Outside of society, they’re waiting for me.”(Rock’n’Roll Nigger, in Patti Smith Group, Easter, 1978)。
2025年3月1日
過去の投稿を読む
著者別アーカイブ
-
- 今との出会い第236回「想いだされ続けるということ――「淵源(ルーツ)」を求めて」
- 今との出会い 第225回「「一休フェス〜keep on 風狂〜」顛末記」
- 今との出会い 第214回「二十年前、即今に在り」
- 今との出会い 第201回「演じる―山崎努と一休に寄せて―」
- 今との出会い 第191回「「寝業師」根本陸夫―「道」を求めし者たちが交わらせるもの―」
- 今との出会い 第181回「 “We shiver and welcome fire” ―シカゴ印象記―」
- 今との出会い 第171回「無知を「批判」的に自覚する契機―「浪人」ということについて―」
- 今との出会い 第162回「遊ぶ子どもの声きけば」
-
- 今との出会い第234回「「適当」を選ぶ私」
- 今との出会い 第230回「本願成就の「場」」
- 今との出会い 第222回「仏教伝道の多様化にいかに向き合うか」
- 今との出会い 第221回「「自由」と「服従」」
- 今との出会い 第218回「思惟ということ」
- 今との出会い 第220回「そういう状態」
- 今との出会い 第211回「#Black Lives Matter ――差別から思うこと」
- 今との出会い 第210回「あの時代の憧憬」
- 今との出会い 第207回「浄土の感覚」
- 今との出会い 第202回「「救い」ということ」
- 今との出会い 第200回「そもそも王舎城で―マガダ国王・頻婆娑羅(ビンビサーラ)考―」
- 今との出会い 第199回「曖昧なブラック」
- 今との出会い 第198回「一瞬の同時成立」
- 今との出会い 第196回「ともしびとなる日々」
- 今との出会い 第194回「星の祝祭を手のひらに」
- 今との出会い 第192回「「共感」の危うさ」
- 今との出会い 第190回「再び王舎城へ―阿難最後の願いと第一結集の開催―」
- 今との出会い 第186回「人生、なるようにしか……」
- 今との出会い 第184回「ひとりの夢を」
- 今との出会い 第182回「遺伝性の疾患等の理由で強制不妊手術が行われていたという報道に触れて思うこと」
- 今との出会い 第180回「地涌の菩薩」をどう読むか
- 今との出会い 第176回「自分との対話」
- 今との出会い 第174回「そしてハイシャはつづく」
- 今との出会い 第172回 「劉暁波氏の訃報にふれて思うこと」
- 今との出会い 第170回「現代へのまなざし」
- 今との出会い 第166回「独り立つ「人」」
- 今との出会い 第164回「誰かと生きる時間」
- 今との出会い 第163回「市場経済とペットの命」