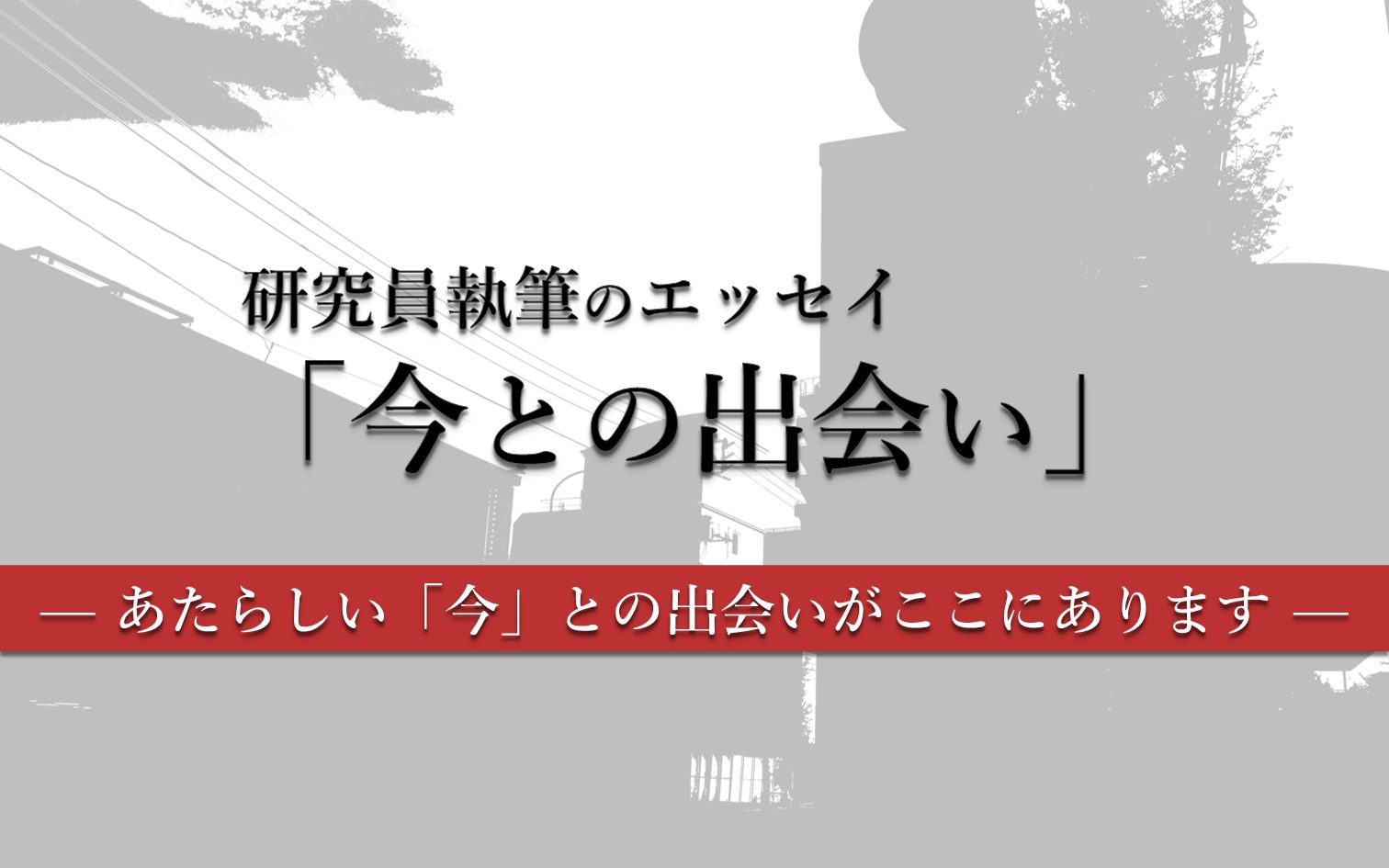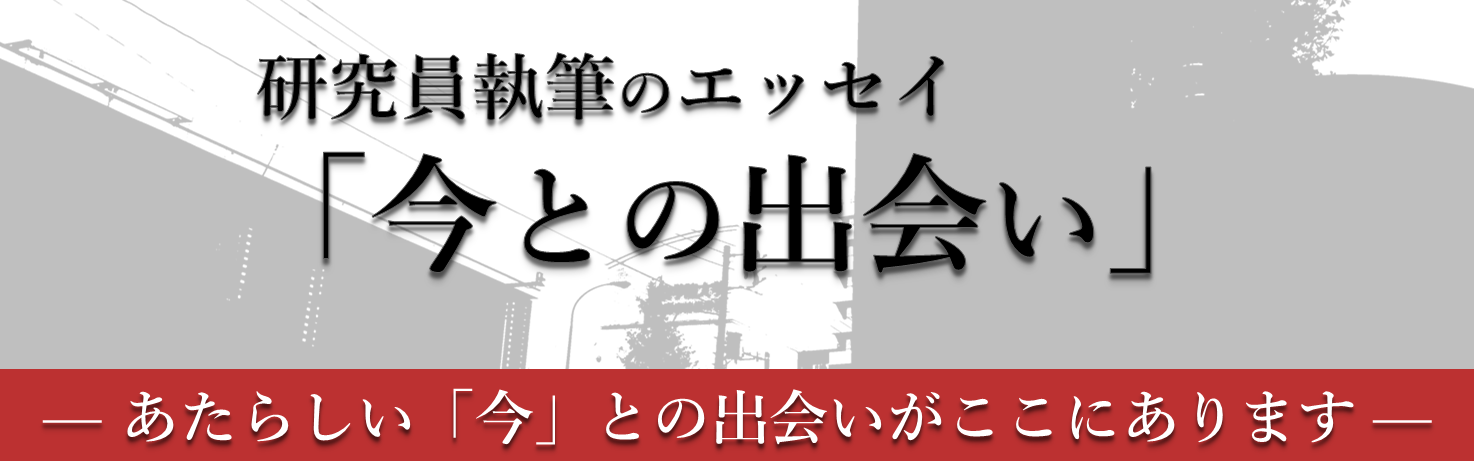
今との出会い第196回「ともしびとなる日々」

親鸞仏教センター研究員
東 真行
(AZUMA Shingyo)
「…いや…… …ええと …うん 日記を …つけはじめるといいかも知れない」
「日記?」
「この先 誰が あなたに何を言って …誰が 何を 言わなかったか あなたが 今… 何を感じて 何を感じていないのか たとえ二度と開かなくても いつか悲しくなったとき それがあなたの灯台になる」
(ヤマシタトモコ『違国日記』第1巻、第2話より)
突然の事故で両親を失った女の子に、その亡き母の妹である女性がこのように語っている。
様々なSNSが横溢する現在、紙媒体の日記に手書きするひとはどれほどいるだろう。少なくとも私はそのひとりではないし、友人たちを思い浮かべてはみるものの見あたらないようだ。
こう書き出してみると、ある思い出がふと去来する。2007年、原美術館で見たヘンリー・ダーガーのことだ。ダーガーは人知れず、2万ページを超える物語原稿と300枚以上の挿絵を遺して生涯を終えていった。かれは自作の原稿を読み返しただろうか。寝る間を惜しんで書き継ぎ、もしかすると2度と開かれないページもあったのではと想像をめぐらせる。同時に、遺されたあらゆるページはかれの生を照らす灯台ではなかったかとも思う。
日記を書くのは、どんなこころなのか。1日の終わりにひとり、まっさらなページに向かう。その日の些事、投げかけられた言葉、感じたことなどを記すとき、ひとは必ずしもひとりではない。メモ程度の日記であれば話は別だが、腰を落ち着けて黙々と書こうとすれば、すでに過去となった出来事が再現され、ひとびとが躍動し語ることもある。他者のみならず、いまあらわされ出づる言葉を読むみずからもまた見出されてくる。さらにはその日記がいずれ誰かに読まれることになる、そんな未来までもが、ペンを走らせるところに訪れている。しばしのあいだ足をとどめ、日々のきめを手探り、あらわす。悠々たる時がそこには流れているのだろうか。
明治期の哲学者であり仏教者、清沢満之は少なからず日記を遺している。岩波書店版の全集でおおよそ400ページ超の文量だから、40年の生涯でそれなりの時間を日記に費やしたといえよう。そのなかでも「臘扇記」(1898年8月より1899年4月までの日記)は間接的または部分的にではあるが、もっともよく読まれた日記といえる。というのは、門弟のひとりである多田鼎が「臘扇記」から言葉をえらび整えた文章「絶対他力の大道」(『精神界』第2巻第6号、1902)は、清沢を仰ぎ慕うひとびとによってよく拝読され、そらんじられてきたからである。
「絶対他力の大道」は清沢の存命中に発表されており、このことから清沢の日記が当時、門弟たちのあいだである程度は共有され、読まれていたことがわかる。部屋でひとり、筆を走らせていたときも、門弟たちのおもかげが清沢のもとを尋ねていたのだろうか。
おそらく清沢自身は、みずからの日記を門弟たちほど繰り返し読むことはなかったし、まして拝読することもなかった。2度と開かないページもあったかもしれない。しかし、日記につづられた言葉は、清沢みずからの悲痛を照らす灯台として、その心中に結晶化されていたのではないか。そして、清沢と等しく人間としての苦悩をいだく門弟たちにとっても、日記に遺された清沢の言葉が、悲しみにあえぐときのともしびとなっていったにちがいない。「絶対他力の大道」はいまなお読み継がれている。
清沢が生きた日々が言葉としてとどまり、門弟たちにかぎらず、多くの者たちの苦悩を照らす灯台となったとは、おどろくべきことである。私たちが生きる1日は、実はそれほどに重たい。私たちが日々絶えず遭遇する悲しみは、私たち自身のともしびとなる日々にあがなわれるほかないのかもしれない。
私たちが生きる日々のきめのなかにすでに、悲しみをいやす答えは見出されているのではないか。私たちはその答えを通りすぎていたのだ。だから、遮二無二に発信するのではなく、みずからの内へともぐることの大切さをいま一度、私は思わずにはいられないでいる。
(2019年9月1日)
最近の投稿を読む

今との出会い第196回「ともしびとなる日々」
2022年9月29日
続きを読む

今との出会い 第232回「漫画の中の南無阿弥陀仏」
2022年9月09日
今との出会い 第232回「漫画の中の南無阿弥陀仏」 親鸞仏教センター嘱託研究員 青柳 英司 (AOYAGI Eishi) 日本の仏教史において、南無阿弥陀仏という言葉が持った意味は極めて重い。 この六字の中に、法然は阿弥陀仏の「平等の慈悲」を発見し、親鸞は一切衆生を「招喚」する如来の「勅命」を聞いた。彼らの教えは、身分を越えて様々な人の支援を受け、多くの念仏者を生み出すことになる。そして、現代においても南無阿弥陀仏という言葉は僧侶だけが知る特殊な用語ではない。一般的な国語辞典にも載っており、広く人口に膾炙(かいしゃ)したものであると言える。…
続きを読む

今との出会い 第231回「病に応じて薬を授く」
2022年8月01日
今との出会い 第231回「病に応じて薬を授く」 親鸞仏教センター主任研究員 加来 雄之 (KAKU Takeshi) 「また次に善男子、仏および菩薩を大医とするがゆえに、「善知識」と名づく。何をもってのゆえに。病を知りて薬を知る、病に応じて薬を授くるがゆえに。」(『教行信証』化身土巻、『真宗聖典』354頁)…
続きを読む

今との出会い 第230回「本願成就の「場」」
2022年6月01日
今との出会い 第230回「本願成就の「場」」 親鸞仏教センター嘱託研究員 中村 玲太 (NAKAMURA Ryota) 「信仰を得たら何が変わりますか?」――訊ねられる毎に苦悶する難問であり、断続的に考えている問題である。これは自身の研究課題とする西山義祖・證空(1177…
続きを読む
No posts found